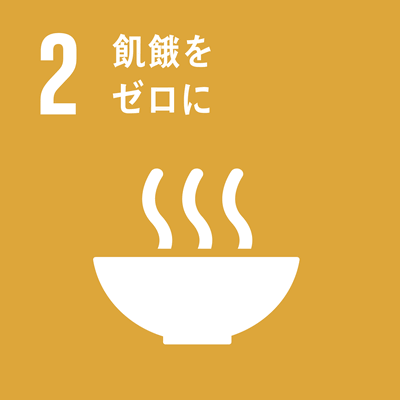シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2023 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 生物資源学部 | |
| 受講対象学生 |
海洋生物資源学科・海洋生物資源学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 |
|
| 選択・必修 | 選択必修 選択科目:水圏P指定科目,海洋P指定科目 |
|
| 授業科目名 | 水族繁殖学 | |
| すいぞくはんしょくがく | ||
| Reproductive Biology of Aquatic Animals | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | BIOR-Mari-2531-006
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期 |
|
| 開講時間 |
月曜日 3, 4時限 |
|
| 授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | ○吉岡 基(生物資源学部海洋生物資源学科),船坂 徳子(生物資源学部海洋生物資源学科) | |
| ○YOSHIOKA, Motoi; FUNASAKA, Noriko | ||
| 実務経験のある教員 | 吉岡基:国立科学博物館および(一財)日本鯨類研究所において,鯨類を中心とした研究活動および管理業務に係る実務職に計3年間従事していた経験を活かし,この講義では,とくに海生哺乳類の繁殖に係る部分について実務的な観点もとりいれて指導する。 船坂徳子:太地町立くじらの博物館において鯨類の研究活動に従事していた経験を活かし,鯨類の繁殖に係る部分について実務的な観点もとりいれて指導する. |
|
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 水生セキツイ動物の繁殖生理と繁殖生態を概説する.生命,環境,食料,健康等に関する生物資源学の基本的な知識と技術と経験を得る目的に向け,1年次までに習得した基礎知識をより深めるため,専門的かつ限定された分野において学修する科目である.具体的には,魚類から海生哺乳類を対象とした繁殖生物学の基礎的内容をとりあげ,同じ水中で生活する動物群間で繁殖生理・生態を比較・解説する.また,これらの内容をする学修する過程において,科学英語により早期に慣れるため,講義でとりあげる題材に関連した学術論文等の一部を教材として使用して学修する. |
|---|---|
| 学修の目的 | 同じ水圏を生活場所とした動物は多様であり,動物群によって生きるためにさまざまな戦略をもっていることを繁殖という側面から知り,かつ理解できるようになる.また,卒業研究に入る前(卒業論文を書き始まる前)に,科学論文(生物学に関する科学英語)をよむとはどういうことかを認識し,実践できるようになる. |
| 学修の到達目標 | 1)魚類から海生哺乳類にいたる水生セキツイ動物における繁殖生理や繁殖生態の特性を理解し,それらの動物群における違いが説明できる. (知識)動物分類群ごとに,同じ観点から,講義で対象とした複数の動物群の繁殖特性の違いを対比・区別して説明ができる. (態度)講義で習得した知識だけではなく,関連する書籍を調べたり,実際の動物を観察するなどの行動を始める. (技能)講義で対象とした動物を野生あるいは飼育下(水族館等)で鑑賞,観察した際,知識として得たことを実際の観察の中で確認したり,感じることができる. 2)基礎的専門用語を英語で理解することができる. (知識)講義で学修した生物学,繁殖生物学,生殖内分泌学の専門用語を日英双方で列記し,訳語を述べることができる. (態度)専門用語についての認識をもち,自分の学習分野(関心のある分野)の専門用語を調べ始める. (技能)生物学に限らず,それぞれの学問分野には専門用語があることを認識した上で,適切なツールを使って用語の意味を調べることができる. 3)科学論文の基本構造について説明ができる. (知識)生物学に関する科学論文がどのような構成になっているか,またそれぞれの構成部分がどのような意味をもっているかを説明することができる. (態度)他の分野においても,学術論文を探したり,読んだりすることを始める. (技能)学術論文の構造を理解し,自分が必要とする学術論文の検索ができる. |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 期末試験(70%)と授業時において指名された場合の解答や適宜実施する小テストの解答(30%),計100%(合計が60%以上で合格). 1)魚類から海生哺乳類にいたる水生生物における繁殖生理や繁殖生態の特性を理解し,それらの動物群における違いが説明できる(期末試験:50%,授業時における解答:10%). (知識)動物分類群ごとに,同じ観点から,講義で対象とした複数の動物群の繁殖特性の違いを対比・区別して説明ができる(期末試験:50%,授業時における解答:10%). (態度)講義で習得した知識だけではなく,関連する書籍を調べたり,実際の動物を観察するなどの行動を始める(期末試験:0%,授業時における解答:0%). (技能)講義で対象とした動物を野生あるいは飼育下(水族館等)で鑑賞,観察した際,知識として得たことを実際の観察の中で確認したり,感じることができる(期末試験:0%,授業時における解答:0%). 2)基礎的専門用語を英語で理解することができる(期末試験:15%,授業時における解答:15%). (知識)講義で学修した生物学,繁殖生物学,生殖内分泌学の専門用語を日英双方で列記し,訳語を述べることができる(期末試験:10%,授業時における解答:10%). (態度)専門用語についての認識をもち,自分の学習分野(関心のある分野)の専門用語を調べ始める(期末試験:5%,授業時における解答:2%). (技能)生物学に限らず,それぞれの学問分野には専門用語があることを認識した上で,適切なツールを使って用語の意味を調べることができる(期末試験:0%,授業時における解答:3%). 3)科学論文の基本構造について説明ができる(期末試験:5%,授業時における解答:5%). (知識)自然科学系論文がどのような構成になっているか,またそれぞれの構成部分がどのような意味をもっているかを説明することができる(期末試験:5%,授業時における解答:5%). (態度)他の分野においても,学術論文を探したり,読んだりすることを始める(期末試験:0%,授業時における解答:0%). (技能)学術論文の構造を理解し,自分が必要とする学術論文の検索ができる(期末試験:0%,授業時における解答:0%). |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) 教員と学生のやり取りは日本語でも、英語による論文や教材の講読を含んだ授業 |
| 授業改善の工夫 | アクティブラーニングの時間を毎回,半分程度取り入れる. |
| 教科書 | 指定せず. 輪読用の英文は,講義時に適宜配付する. |
| 参考書 | 魚類生理学の基礎(会田勝美編,恒星社厚生閣),哺乳類の生殖生物学(高橋迪雄監修,学窓社),動物生理学(ニールセン,東京大学出版会),ウミガメの自然誌 (亀崎直樹,東京大学出版会),ペンギン・ペディア(サロモン,河出書房新社),海の哺乳類 : その過去・現在・未来. 増補版(宮崎・粕谷編,サイエンティスト社) |
| オフィスアワー | 随時可能(612室) メールにより,事前予約をしてください(motoi@bio.) |
| 受講要件 | とくになし. 科学英語論文の基本構成を理解し,英語論文に早くなれたいと思っている人. |
| 予め履修が望ましい科目 | 生理学 海洋生物資源学概論 |
| 発展科目 | 魚類増殖学,海生哺乳動物学,海生哺乳動物学実習 |
| その他 |
環境教育に関連した科目 |
授業計画
| 各回 共通 |
MoodleのコースURL |
|---|
| 第1回 | 概要 | 繁殖生物学とは?① |
|---|---|---|
| 授業時間内の学修内容 | 講義概要の説明,生殖と繁殖,繁殖生物学とは? 学術論文の構造 |
|
| キーワード(Key Word(s)) | 生殖(reproduction),繁殖(reproduction),繁殖生物学(reproductive biology),学術論文(scientific papers) | |
| 事前学修の内容 | 生殖と繁殖の違い,理学と農学における生殖の捉え方の違いを調べておく. | |
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 講義で説明した用語(術語)の整理. 配付した次回輪読用資料の予習(英文和訳と内容理解). |
|
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第2回 | 概要 | 繁殖生物学とは? ② |
| 授業時間内の学修内容 | 生殖機能系,生殖ホルモン 関連する学術論文の英文要旨の輪読 |
|
| キーワード(Key Word(s)) | 生殖機能系(reproductive system),生殖ホルモン(reproducitve hormone),下垂体(pituitary),生殖腺(gonad) | |
| 事前学修の内容 | ホルモンとは何か,そのうち繁殖に関するホルモンにはどのようなものがあるか調べておく. 前回配付された学術論文の英文要旨の和訳の作成と内容理解. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 講義で説明した用語の整理. 講義で輪読した内容の理解と訳文の必要な修正. |
|
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第3回 | 概要 | 繁殖生物学とは? ③ |
| 授業時間内の学修内容 | 繁殖周期と性周期,繁殖システム 関連する学術論文の英文要旨の輪読 |
|
| キーワード(Key Word(s)) | 繁殖周期(reproductive cyle),性周期(sexual cycle),繁殖システム(reproductive system) | |
| 事前学修の内容 | 動物の繁殖戦略にはどのようなものがあるか,調べておく. 前回配付された学術論文の英文要旨の和訳の作成と内容理解. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 講義で説明した専門用語の整理と用語集の更新. 講義で輪読した内容の理解と訳文の必要な修正. |
|
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第4回 | 概要 | 魚類の繁殖 ① |
| 授業時間内の学修内容 | さまざまな生殖様式と魚類の生殖様式,性分化. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | 有性生殖(sexual reproduction),可塑性(plasticity),性転換(sex change) | |
| 事前学修の内容 | 動物の生殖に見られるさまざまな様式について調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. | |
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第5回 | 概要 | 魚類の繁殖 ② |
| 授業時間内の学修内容 | 硬骨魚類の繁殖-生殖腺(卵巣)の構造と発達. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | 卵巣(ovary),卵母細胞(oocyte),生殖腺体指数(GSI) | |
| 事前学修の内容 | 硬骨魚類の卵巣の成熟過程についてどのような細胞がかかわっているか調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. | |
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第6回 | 概要 | 魚類の繁殖 ③ |
| 授業時間内の学修内容 | 硬骨魚類の繁殖-生殖腺(精巣)の構造と発達. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | 精巣(testis),精子(sperm),精母細胞(spermatocyte),GSI | |
| 事前学修の内容 | 硬骨魚類の精巣の成熟過程についてどのような細胞がかかわっているか調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. | |
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第7回 | 概要 | 魚類の繁殖 ④ |
| 授業時間内の学修内容 | 軟骨魚類の種類と基礎生態. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | サメ(shark),エイ(ray),卵生(oviparity),胎生(viviparity) | |
| 事前学修の内容 | 軟骨魚類とはどのような魚類か,またどのような種類があるか調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. | |
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第8回 | 概要 | 魚類の繁殖 ⑤ |
| 授業時間内の学修内容 | 軟骨魚類の繁殖-多様な繁殖様式. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | サメ(shark),エイ(ray),卵生(oviparity),胎生(viviparity) | |
| 事前学修の内容 | 卵生,胎生,卵胎生の用語が板鰓類についてどのように現在取り扱われているか調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. 週末などの時間を使って,水族館で魚類の繁殖に関する解説を読むとともに実際の動物を観察する. |
|
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第9回 | 概要 | ウミガメ類の繁殖 ① |
| 授業時間内の学修内容 | ウミガメ類の種類と基礎生態. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | ウミガメ(sea turtle),IUCN,レッドリスト(red list) | |
| 事前学修の内容 | ウミガメの種類や現在の生息状況について調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. | |
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第10回 | 概要 | ウミガメ類の繁殖 ② |
| 授業時間内の学修内容 | ウミガメ類の繁殖生態. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | TSD,性比(sex ratio),地球温暖化(global warming) | |
| 事前学修の内容 | 爬虫類における発生様式について調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. 週末などの時間を使って,水族館でウミガメの繁殖に関する解説を読むとともに実際の動物を観察する. |
|
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第11回 | 概要 | 海鳥類の繁殖 ① |
| 授業時間内の学修内容 | 海鳥の種類と基礎生態. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | 海鳥(sea bird),IUCN,レッドリスト(red list) | |
| 事前学修の内容 | 海鳥にはどのような動物が含まれるか調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. | |
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第12回 | 概要 | 海鳥類の繁殖 ② |
| 授業時間内の学修内容 | ペンギン類の繁殖生態. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | ペンギン(penguin),クレイシ(creche),トレードオフ(trade off), | |
| 事前学修の内容 | ペンギンの種類と分布について調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. 週末などの時間を使って,水族館でペンギンの繁殖に関する解説を読むとともに実際の動物を観察する. |
|
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第13回 | 概要 | 海生哺乳類の繁殖 ① |
| 授業時間内の学修内容 | 鰭脚類と海牛類の繁殖. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | アシカ(sea lion),アザラシ(seal),ジュゴン(dugon),マナティ(manatee),半水生(semi-aquatic),繁殖様式(reproductive sysutem),コロニー(colony),ハーレム(harem),草食動物(harnivore) | |
| 事前学修の内容 | 海生哺乳類にはどのような動物が含まれているか,これまでの履修した講義内容から復習しておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. | |
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第14回 | 概要 | 海生哺乳類の繁殖 ② |
| 授業時間内の学修内容 | ヒゲクジラ類の繁殖. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | ヒゲクジラ類(baleen whale),性成熟(sexual maturity),繁殖周期(reproductive cycle),繁殖様式(reproductive system),生活史(life history),回遊(migration) | |
| 事前学修の内容 | ヒゲクジラの種類と分布について調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学修の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. | |
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 | ||
| 第15回 | 概要 | 海生哺乳類の繁殖 ③ |
| 授業時間内の学修内容 | ハクジラ類の繁殖. 関連する学術論文の英文要旨の輪読. |
|
| キーワード(Key Word(s)) | ハクジラ類(toothed whale),イルカ(dolphin),性成熟(sexual maturity),排卵(ovulation),性周期(estrous cycle),繁殖様式(reproductive system),生活史(life history) | |
| 事前学修の内容 | ハクジラの種類と分布について,ヒゲクジラと対比しながら調べておく. 前回講義時に配付した資料の和訳を行い,専門用語を整理しておくとともに,内容を理解しておく. |
|
| 事前学修の時間 | 120分 | |
| 事後学修の内容 | 事前学習の結果と講義による解説を受けての訳文の修正を行い,専門用語集の更新を行う. 週末などの時間を使って,水族館で鯨類の繁殖に関する解説を読むとともに実際の動物を観察する. |
|
| 事後学修の時間 | 120分 | |
| 自由記述欄 |