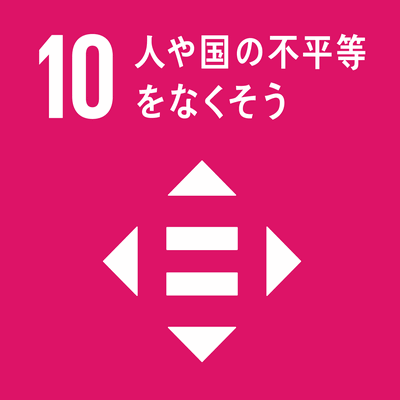シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2023 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文学部文化学科 | |
| 受講対象学生 |
2011年度以前入学生用(文化) 学部(学士課程) : 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 |
|
| 選択・必修 | 選択 |
|
| 授業科目名 | 日本文学演習I | |
| にほんぶんがくえんしゅう | ||
| Japan Literature Seminar I | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | humn-cult2100-106
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期 |
|
| 開講時間 |
木曜日 5, 6時限 |
|
| 授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 尾西康充(人文学部) | |
| ONISHI,Yasumitsu | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 日本近代文学の作品を資料を用いながら講読する。文化学科のカリキュラムの中では、日本地域の文化をさらに深く理解するために必要な科目です。さらに日本近代文学を研究するための基本的な手法と知識を修得します。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 文学作品の講読を通じて、日本文学・日本文化に関する知識を得るとともに、さまざまな文献を客観的に読み解く力を身に付けます。 |
| 学修の到達目標 | 文学作品のモチーフやテーマを読解したうえで、テキストを素材に主体的に考え、論理的に自分の意見を主張できるようになります。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 授業中のプレゼンテーション30%、レポート30%、期末試験40% |
| 授業の方法 | 演習 |
| 授業の特徴 |
プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 Moodleを活用する授業 |
| 授業改善の工夫 | |
| 教科書 | 『日本近代短篇小説選 明治篇1』(岩波文庫) |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 毎週木曜日12時~13時 |
| 受講要件 | |
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 日本近代文学 |
|---|---|
| Key Word(s) | Japan Modern Literature |
| 学修内容 | 演習形式で事前に準備した資料にもとづいて発表し、受講生全員で討議する。 第1・2回:発表分担の決定、レジュメの作り方、文献収集法、基礎知識の確認など 第3回:細君 / 坪内逍遥 著 第4回:くされたまご / 嵯峨の屋おむろ 著 第5回:この子 / 山田美妙 著 第6回:舞姫 / 森鷗外 著 第7回:拈華微笑 / 尾崎紅葉 著 第8回:対髑髏 / 幸田露伴 著 第9回:こわれ指環 / 清水紫琴 著 第10回:かくれんぼ / 斎藤緑雨 著 第11回:わかれ道 / 樋口一葉 著 第12回:龍潭譚 / 泉鏡花 著 第13回:武蔵野 / 国木田独歩 著 第14回:雨 / 広津柳浪 著 第15回:まとめと学修のふりかえり |
| 事前・事後学修の内容 | 授業を受ける前に、かならず各回の作品を読んでおいてください。さらに作者や作品の知識を身に付けておいてください。 授業を受けた後は、もう一度作品を読み直すとともに、同じ作者の他の作品を読んでみてください。 |
| 事前学修の時間:60分/回 事後学修の時間:60分/回 |