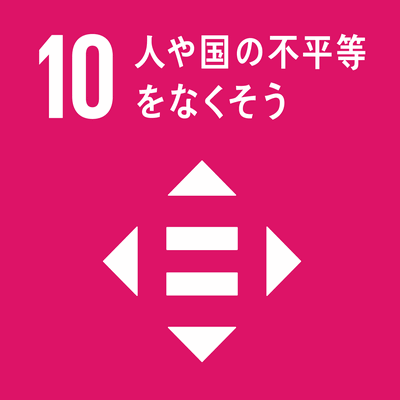シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2023 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 地域イノベーション学研究科(博士後期課程) | |
| 受講対象学生 |
大学院(博士課程・博士後期課程) : 1年次 |
|
| 選択・必修 | 選択 |
|
| 授業科目名 | 地域新創造特論ⅩⅢ | |
| ちいきしんそうぞうとくろん じゅうさん | ||
| Regional Development ⅩⅢ | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | inov-inov-INOV-7-0-3-3-013
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
通年 |
|
| 開講時間 |
水曜日 1, 2時限 履修者と調整して決める |
|
| 授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 水木千春 | |
| MIZUKI, Chiharu | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 自然災害や防災をおもなテーマとして、地域における課題抽出(情報収集、発表、討論、記述)を行い、研究に必要な総合的なスキルを習得する。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 自然災害や防災をテーマとした地域課題に関する調査をデザインできる。 |
| 学修の到達目標 | 意識調査(フィールドワーク)を取り入れた研究を進めるために必要な基礎知識から実践的な知識まで得ることができる。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 発表(30%)、議論への参加状況(30%)、レポート(40%)、計100%。(合計が60%以上で合格) |
| 授業の方法 | 講義 演習 |
| 授業の特徴 |
プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 グループ学習の要素を加えた授業 地域理解・地域交流の要素を加えた授業 |
| 授業改善の工夫 | 学生が能動的に研究を進められるよう、授業の内容を工夫し、適宜改善する |
| 教科書 | とくになし |
| 参考書 | 必要に応じ提示する |
| オフィスアワー | メールにて日時を調整し対応する |
| 受講要件 | とくになし |
| 予め履修が望ましい科目 | とくになし |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 行動科学分析、防災意識、地域課題、フィールドワーク |
|---|---|
| Key Word(s) | Behavioral science analysis, Disaster prevention awareness, Local issues, Field work |
| 学修内容 | 第1回 ガイダンス(必要であればスケジュール調整) <情報収集と伝達:ハザードとリスクの関係> 第2回 ハザードに関する情報:気象情報・マスメディア・SNS ・講義と演習形式 第3回 リスク認知:災害情報・避難情報・災害心理 ・講義と演習形式 <行動科学に基づいた意識調査(フィールドワーク)> 第4回 講義 第5回 演習「調査のデザインとその手法」 <研究テーマの整理・課題設定> 第6回~第9回 先行研究・論文のレビュー、調査項目の提案・検討 ・発表と討論 <調査状況報告・分析方法の検討> 第10回~第12回 調査の進捗状況報告、分析方法の提案・検討 ・発表と討論 <分析結果報告> 第13回、第14回 分析結果の報告と分析方法の再検討 ・発表と討論 <まとめ> 第15回 調査に関する発表、今後の課題 ・発表と討論 ・総括 |
| 事前・事後学修の内容 | 事前:発表や他の学生とのディスカッションにより、理解を深める授業のため、発表に関する資料の準備をする。また予め示すテーマについての予習も必要である。 事後:発表内容の見直しや、議論の中から得られた知見についてまとめておき、疑問点があれば、整理しておく。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |