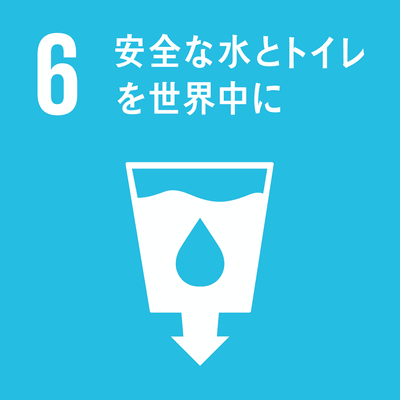シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2023 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 生物資源学研究科(博士前期課程)共生環境学専攻 | |
| 受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次 |
|
| 選択・必修 | 選択必修 |
|
| 授業科目名 | 未来海洋予測学演習 | |
| みらいかいようよそくがくえんしゅう | ||
| Seminar on atmospheric and oceanic fluid dynamics | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | BIOR-Envr-5172-004
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
後期集中 |
|
| 開講時間 |
木曜日 7, 8時限 |
|
| 授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 万田敦昌(生物資源学研究科共生環境学専攻) | |
| MANDA, Atsuyoshi | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 本講義では専門書の精読, その内容に関する議論, 問題演習を行うことによって,海洋と大気における流動のメカニズムを研究するための基礎知識を習得する。海洋と大気の流動は自然環境を制御する重要な過程であり,その特性を理解することは,様々な生産活動において,自然環境の変化に適切に対応するために必要不可欠な能力である。本講義で学習した内容は,地球環境学特別研究 I, 地球環境学特別研究IIを履修する際に必要な知識となる。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 自然界に存在する風や海流等の流れは生物の生息環境に大きな影響を与える。本講義の目的は大気・海洋の流れを支配する自然法則を正しく認識し, その自然法則を適用することで流れのメカニズムを論考するための基礎知己を習得ことである。このことは種々の生産活動における環境変化への対応策を立案・実施するために必要不可欠な能力である。 |
| 学修の到達目標 | (知識) 流れに関わる自然法則を数式,文章,および図を使って説明することができる (態度) 流れのメカニズムを数式, 文章, 図表で表現することができる (技能) 流れに関わる自然法則を用いて流れの特性を調べることが出来る。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 講義への参加状況50%, 課題50%. 計100% (合計が60%以上で合格) (知識) 流れに関わる基本的な自然法則を文章,数式,図を使って説明することができるか,講義への参加状況と課題で評価する。 (態度) 流れのメカニズムを,自然法則に基づいて数式, 文章, 図表で表現することができるか, 講義への参加状況と課題で評価する。 (技能) 自然法則に基づいて流れの特性を調べることが出来るか,講義への参加状況と課題で評価する。 |
| 授業の方法 | 講義 演習 |
| 授業の特徴 |
問題自己設定型PBL プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 教員と学生、学生相互のやり取りの一部が英語で進められる授業 教員と学生のやり取りは日本語でも、英語による論文や教材の講読を含んだ授業 |
| 授業改善の工夫 | ディスカッションへの積極的な参加を促す.また,発表と質疑応答によって各自の理解を深める. |
| 教科書 | ジョナサン E. マーティン (2016): 大気力学の基礎 中緯度の総観気象, 東京大学出版会. |
| 参考書 | Jonathan E. Martin (2006): Mid-Latitude Atmospheric Dynamics A First Course, Willy. 小倉義光 (2000): 総観気象学入門, 東京大学出版会. H. Bluestein, 1992. Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes: Volume I: Principles of Kinematics and Dynamics, Oxford University Press, 448pp. H. Bluestein, 1992. Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes: Volume II: Observations and Theory of Weather Systems, Oxford University Press, 608pp. |
| オフィスアワー | メール(am@bio.mie-u.ac.jp)でのアポイントメントを取ることが望ましい. |
| 受講要件 | 数学に関しては,線形代数,多変数の微分・積分,ベクトル解析に関する学部レベルの知識を必要とする。物理学に関しては,質点の力学,流体力学の学部レベルの知識を必要とする。 |
| 予め履修が望ましい科目 | 未来海洋予測学特論・気象解析予測学特論 |
| 発展科目 | 気象解析予測学演習 |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 地球流体力学,海洋学,気象学 |
|---|---|
| Key Word(s) | Geophysical Fluid Dynamics |
| 学修内容 | 授業計画(各回形式) 第1回 概要:序論および数学的道具の概観 授業時間内の学修内容 : ・流体と流体力学の性質 ・有用な数学的道具の外観 ・スケール解析による推定 ・渦度 ・発散 ・伸長 ・シア― キーワード(Key Word(s)): ・Fluid, Hydrodynamics, mathematical tools 事前学修の内容 : 教科書の問題文を分析し, 問題を解くために必要な予備知識をまとめる。問題を解く。 ○ 事前学修の時間(分)240 事後学修の内容: 問題を解きなおし,問題を解くために必要な予備知識と解答を記載したレポートを作成する. ○ 事後学修の時間(分)480 第2回 概要 : 真の力とみかけの力 授業時間内の学修内容 : ・気圧傾度力 ・引力 ・摩擦力 ・遠心力 ・コリオリ力 キーワード(Key Word(s)): ・Force 事前学修の内容 : 教科書の問題文を分析し, 問題を解くために必要な予備知識をまとめる。問題を解く。 ○ 事前学修の時間(分)240 事後学修の内容: 問題を解きなおし,問題を解くために必要な予備知識と解答を記載したレポートを作成する. ○ 事後学修の時間(分)480 第3回 質量,運動量およびエネルギー 概要 : 基本法則 授業時間内の学修内容 : ・大気中の質量 ・運動量の保存 ・エネルギーの保存 キーワード(Key Word(s)): ・Fundamental laws in hydrodynamics 事前学修の内容 : 教科書の問題文を分析し, 問題を解くために必要な予備知識をまとめる。問題を解く。 ○ 事前学修の時間(分)240 事後学修の内容: 問題を解きなおし,問題を解くために必要な予備知識と解答を記載したレポートを作成する. ○ 事後学修の時間(分)480 第4回 概要 : 運動方程式の適用 授業時間内の学修内容 : ・気圧座標系 ・温位座標系 ・地衡流 ・慣性流 ・旋衡流 ・傾度流 ・流跡線と流線 キーワード(Key Word(s)): ・Elementary applications of momentum equation 事前学修の内容 : 教科書の問題文を分析し, 問題を解くために必要な予備知識をまとめる。問題を解く。 ○ 事前学修の時間(分)240 事後学修の内容: 問題を解きなおし,問題を解くために必要な予備知識と解答を記載したレポートを作成する. ○ 事後学修の時間(分)480 第5回 概要 : 循環,渦度および発散 授業時間内の学修内容 : ・循環定理 ・渦度と渦位 ・渦度と発散の関係 ・準地衡方程式系 キーワード(Key Word(s)): ・circulation theorem, vorticity, quasi-geostrophic model 事前学修の内容 : 教科書の問題文を分析し, 問題を解くために必要な予備知識をまとめる。問題を解く。 ○ 事前学修の時間(分)240 事後学修の内容: 問題を解きなおし,問題を解くために必要な予備知識と解答を記載したレポートを作成する. ○ 事後学修の時間(分)480 第6回 概要 : 中緯度総観規模の鉛直運動の診断 授業時間内の学修内容 : ・非地衡風の性質 ・サトクリフの発達定理 ・準地衡オメガ方程式 ・Qベクトル キーワード(Key Word(s)): Ageostrophic motion, quasi-geostrophic omega equation, Q-vector 事前学修の内容 : 教科書の問題文を分析し, 問題を解くために必要な予備知識をまとめる。問題を解く。 ○ 事前学修の時間(分)240 事後学修の内容: 問題を解きなおし,問題を解くために必要な予備知識と解答を記載したレポートを作成する. ○ 事後学修の時間(分)480 第7回 概要 : 前線における鉛直循環 授業時間内の学修内容 : ・中緯度前線の構造と力学的特性 ・前線形成と鉛直運動 キーワード(Key Word(s)): ・Front and frontal circulation 事前学修の内容 : 教科書の内容を説明するための資料を作成する.資料には必要に応じて数式,図表を添付する。 ○ 事前学修の時間(分)480 事後学修の内容: 講義内容, 質問, その回答, 補足説明をまとめたレポートを作成する. ○ 事後学修の時間(分)240 第8回 概要 : 前線強化と降水 授業時間内の学修内容 : ・セミ地衡方程式 ・上層における前線形成 ・前線における降水過程 キーワード(Key Word(s)): ・Frontogenesis and precpitation 事前学修の内容 : 教科書の内容を説明するための資料を作成する.資料には必要に応じて数式,図表を添付する。 ○ 事前学修の時間(分)480 事後学修の内容: 講義内容, 質問, その回答, 補足説明をまとめたレポートを作成する.問題を解き, その回答をまとめたレポートを作成する。 ○ 事後学修の時間(分)240 第9回 概要 : 温帯低気圧の概観 授業時間内の学修内容 : ・低気圧の構造とエネルギー キーワード(Key Word(s)): ・Mid-latitude cyclone 事前学修の内容 : 教科書の内容を説明するための資料を作成する.資料には必要に応じて数式,図表を添付する。 ○ 事前学修の時間(分)480 事後学修の内容: 講義内容, 質問, その回答, 補足説明をまとめたレポートを作成する.問題を解き, その回答をまとめたレポートを作成する。 ○ 事後学修の時間(分)240 第11回 概要 : 低気圧発生 授業時間内の学修内容 : ・準地衡傾向方程式による診断 ・準地衡オメガ方程式による診断 キーワード(Key Word(s)): ・Analysis of the cyclogenesis using quasi-geostrophic models 事前学修の内容 : 教科書の内容を説明するための資料を作成する.資料には必要に応じて数式,図表を添付する。 ○ 事前学修の時間(分)480 事後学修の内容: 講義内容, 質問, その回答, 補足説明をまとめたレポートを作成する.問題を解き, その回答をまとめたレポートを作成する。 ○ 事後学修の時間(分)240 第12回 概要 : 低気圧発達 授業時間内の学修内容 : ・低気圧発達における非断熱過程の影響 ・閉塞 キーワード(Key Word(s)): ・diabatic effects, occluded front 事前学修の内容 : 教科書の内容を説明するための資料を作成する.資料には必要に応じて数式,図表を添付する。 ○ 事前学修の時間(分)480 事後学修の内容: 講義内容, 質問, その回答, 補足説明をまとめたレポートを作成する.問題を解き, その回答をまとめたレポートを作成する。 ○ 事後学修の時間(分)240 第13回 概要 : 渦位 授業時間内の学修内容 : ・温位座標系での渦位 ・正の渦位偏差の特性 キーワード(Key Word(s)): ・potential vorticity 事前学修の内容 : 教科書の内容を説明するための資料を作成する.資料には必要に応じて数式,図表を添付する。 ○ 事前学修の時間(分)480 事後学修の内容: 講義内容, 質問, その回答, 補足説明をまとめたレポートを作成する.問題を解き, その回答をまとめたレポートを作成する。 ○ 事後学修の時間(分)240 第14回 概要 : 渦位を用いた低気圧の解析 授業時間内の学修内容 : ・渦位の視点からの低気圧発生 ・渦位に及ぼす非断熱加熱の効果 キーワード(Key Word(s)): ・potential vorticity thinking 事前学修の内容 : 教科書の内容を説明するための資料を作成する.資料には必要に応じて数式,図表を添付する。 ○ 事前学修の時間(分)480 事後学修の内容: 講義内容, 質問, その回答, 補足説明をまとめたレポートを作成する.問題を解き, その回答をまとめたレポートを作成する。 ○ 事後学修の時間(分)240 第15回 概要 : 渦位解析の適用例 授業時間内の学修内容 : ・渦位の分割逆変換 ・閉塞に関する渦位の始点 ・山脈の風下での低気圧発生に関する渦位の始点 ・渦位の重ね合わせと減衰の効果 キーワード(Key Word(s)): ・Applications of the potential vorticity thinking 事前学修の内容 : 教科書の内容を説明するための資料を作成する.資料には必要に応じて数式,図表を添付する。 ○ 事前学修の時間(分)480 事後学修の内容: 講義内容, 質問, その回答, 補足説明をまとめたレポートを作成する.問題を解き, その回答をまとめたレポートを作成する。 ○ 事後学修の時間(分)240 |
| 事前・事後学修の内容 | 事前学修の内容 : 教科書の内容を説明するための資料を作成する.資料には必要に応じて数式,図表を添付する。 ○ 事前学修の時間 6時間x15=80時間 事後学修の内容: 講義内容, 質問, その回答, 補足説明をまとめたレポートを作成する.問題を解き, その回答をまとめたレポートを作成する。 ○ 事後学修の時間 4時間x15=60時間 |
| 事前学修の時間:480分/回 事後学修の時間:240分/回 |