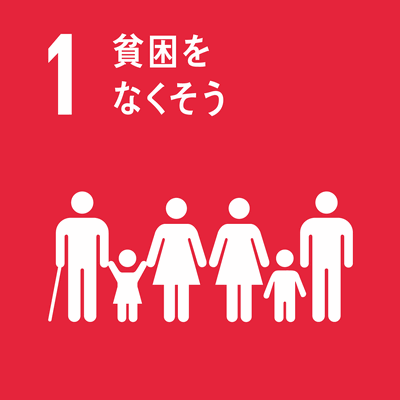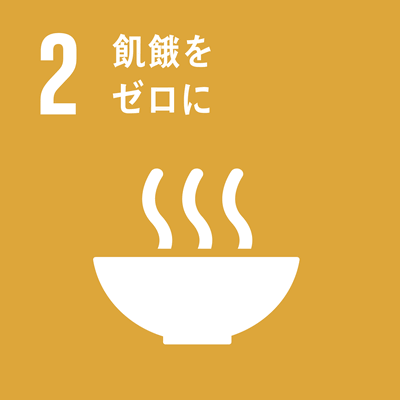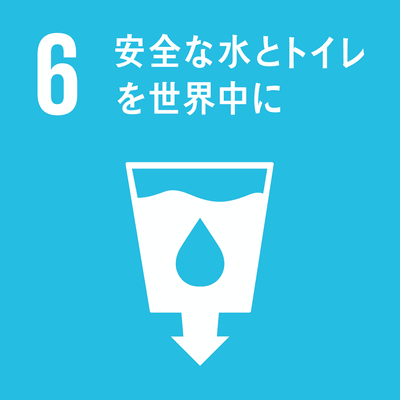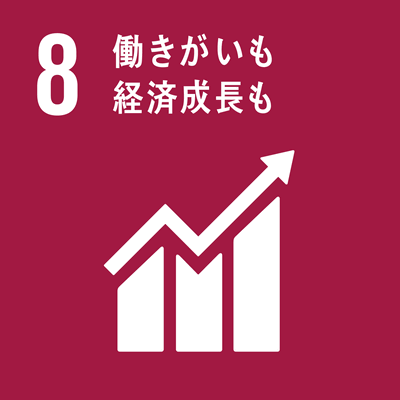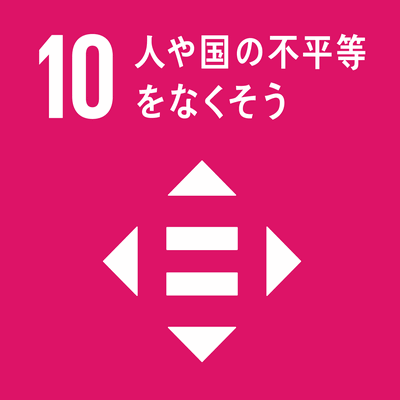シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2022 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 生物資源学研究科(博士後期課程)共通科目 | |
| 受講対象学生 |
大学院(博士課程・博士後期課程) : 1年次, 2年次, 3年次 |
|
| 選択・必修 | 選択 |
|
| 授業科目名 | 持続可能な地球システム論 | |
| じぞくかのうなちきゅうしすてむろん | ||
| Sustainable Earth System | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | 56401
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期集中 集中講義形式です.日程は問い合わせてください |
|
| 開講時間 |
|
|
| 授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | 開講時にアナウンスします | |
| 担当教員 | 坂本竜彦 | |
| Tatsuhiko Sakamoto | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 本講義では,持続可能とは何か,を,エネルギー,水,食糧,産業生産,社会システム等を事例として,実社会における人類的課題,地域的課題について考察します.本講義は,生物資源を取り扱う生物資源学研究科において,根本的な概念としての『持続可能な地球システム」を学びます. |
|---|---|
| 学修の目的 | 学習の目的として,①持続可能性とは何か,②なぜ持続可能性が問われるのか,③産業革命以降の人類の生産・消費活動のあり方,④成長の限界,⑤日本における化石燃料依存社会,⑥自然エネルギーの概要.⑦自然エネルギー社会の基本原則,⑧地域循環社会,⑨エネルギー自給自足社会,⑩未来への展望,などの知識を得て,実践的なヴィジョンを持つこと. |
| 学修の到達目標 | 学習の到達目標として,①持続可能性とは何か,②なぜ持続可能性が問われるのか,③産業革命以降の人類の生産・消費活動のあり方,④成長の限界,⑤日本における化石燃料依存社会,⑥自然エネルギーの概要.⑦自然エネルギー社会の基本原則,⑧地域循環社会,⑨エネルギー自給自足社会,⑩未来への展望,などの知識を得る.また,実践的なヴィジョンを持つことができること. |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | レポート100% |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
プロジェクト型PBL プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 Moodleを活用する授業 教員と学生、学生相互のやり取りの一部が英語で進められる授業 |
| 授業改善の工夫 | |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | メールにてまずは問い合わせること。 tats@bio. |
| 受講要件 | |
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | |
|---|---|
| Key Word(s) | |
| 学修内容 | 第1回 持続可能性とは何か 第2回 なぜ持続可能性が問われるのか 第3回 産業革命以降の人類の生産・消費活動 第4回 成長の限界 第5回 日本における化石燃料依存社会 第6回 地域資源としての自然エネルギーの概要 第7回 自然エネルギー社会の基本原則 第8回 自然エネルギーによる地域循環社会 第9回 自然エネルギーによる自給自足社会 第10回 太陽エネルギーとその利活用 第11回 風力エネルギーとその利活用 第12回 海洋エネルギーとその利活用 第13回 木質バイオマスエネルギーとその利活用 第14回 湿潤系バイオマスエネルギーとその利活用 第15回 未来への展望 |
| 事前・事後学修の内容 | 第1回 持続可能性とは何か 第2回 なぜ持続可能性が問われるのか 第3回 産業革命以降の人類の生産・消費活動 第4回 成長の限界 第5回 日本における化石燃料依存社会 第6回 地域資源としての自然エネルギーの概要 第7回 自然エネルギー社会の基本原則 第8回 自然エネルギーによる地域循環社会 第9回 自然エネルギーによる自給自足社会 第10回 太陽エネルギーとその利活用 第11回 風力エネルギーとその利活用 第12回 海洋エネルギーとその利活用 第13回 木質バイオマスエネルギーとその利活用 第14回 湿潤系バイオマスエネルギーとその利活用 第15回 未来への展望 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |