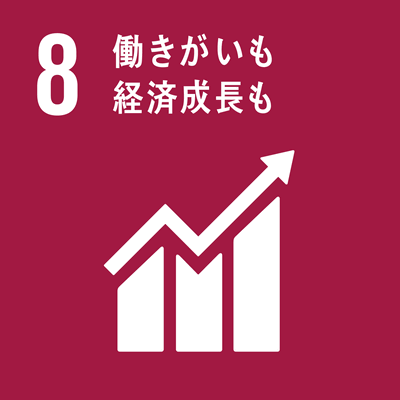シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2021 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 生物資源学部 | |
| 受講対象学生 |
共生環境学科・農業土木学教育コース 学部(学士課程) : 3年次 農業土木系の業界への就職を検討している他コース他学科の学生にも参考になる講義であるため,担当教員への相談があれば受講を認める. |
|
| 選択・必修 | 選択 |
|
| 授業科目名 | 農業土木学キャリアアップ演習 | |
| のうぎょうどぼくがくきゃりああっぷえんしゅう | ||
| Career up Exercise for Irrigation, Drainage and Rural Engineering | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | BIOR-Envi-3342-002
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
水曜日 9, 10時限 |
|
| 授業形態 |
オンライン授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 岡島賢治(生物資源学部共生環境学科) | |
| OKAJIMA Kenji | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 当科目は前期開講科目「実践農業土木学」の応用編として位置づけている。農業土木学教育コースにおいて必要な農業土木系技術の実践的内容を材料として授業を行う。農業農村地域に発生する問題・課題・解決策がどのような経緯・手法で実施されたかを解説する。これらの話題をもとにして、受講生の斬新なアイデアを引き出し、「問題解決法を考えること」を期待する。 そのための手段として、「地域の自然環境と人間活動の共生」に着目し、自然環境を維持しながら人間活動を発展させていくために必要な知識・技術や能力を得て生かすためのトレーニングを行う。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 農業農村地域に発生する問題・課題・解決策がどのような経緯・手法で実施されたかを理解する。 |
| 学修の到達目標 | 幅広い教養と国際性を持ち、技術者倫理を身につける。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 各回に課されるレポートで評価する(レポート100%) |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
キャリア教育の要素を加えた授業 |
| 授業改善の工夫 | |
| 教科書 | とくに指定しない(資料がある場合授業中に配布) |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | okajima@bio.mie-u.ac.jp |
| 受講要件 | 特別な要件は必要としない。 農業土木系への就職を検討しているのであれば,他コース,他学科生が受講しても大いに参考になる |
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 農業土木系技術、実践的内容、第一線現場、公共事業の実際、地域保全に関する実際、国際的事業の展開 |
|---|---|
| Key Word(s) | agricultural engineering technology, practical content, front-line field, public works, conservation area, international development |
| 学修内容 | 農林水産省事業現場、国土交通省事業現場、民間企業事業現場等についての説明を聞き、可能であれば見学を行う。その他、教員から説明して紹介される現地見学会あるいは研究集会等への参加、学外者(非常勤講師等)による実務的な内容についての講義を聴講した後、技術者倫理についてのレポート作成などを行う。具体的な授業内容は、最初の講義で説明する。 <過去の事例> 1.「農業農村工学キャリアアップ演習」を考える(授業の方法と取り組み方) 2.「農業農村工学技術者の育成に官民学のトライアングルを使おう」 3.「面接のこころえ」(国家公務員の事例) 4.「農業農村の人々を支える施策づくりと実行力-地方行政の概要- 5.「ものづくりの最前線!スーパーゼネコンの仕事とは?」 6.「農林水産省の任務と東海農政局の役割」 7.「食の安全と行政の取組」(東海農政局消費生活課) 8.「国家公務員採用試験に向けた準備(事例)と若手職員の活躍」 9.「国家公務員総合職のキャリアパスについて」 10.「農業農村整備事業にかかわる民間企業の役割分担・仕事内容」 11.「農業農村整備にかかる「行政」と「農業土木系技術者」の役割」 12.「農業農村整備における産官学の役割分担と効果的な進め方」 13.「農業農村整備事業における土地改良事業団体連合会の役割について」 14. 現地見学「現場を通して農業土木の役割・重要性を実感する」 15.「国土交通省による取組について」 16.「県土整備部の役割について」 |
| 事前・事後学修の内容 | 各回ごとの講義テーマについて事前学習を課す.また,授業ノートをもとにしっかり復習を行うこと。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |