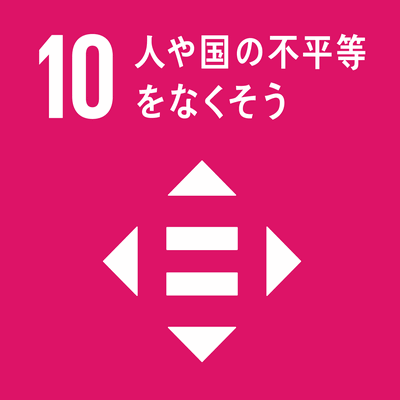シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2021 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 教育学部・学校教育に関する専門科目(A類) | |
| 科目名 | 教育心理学研究法 | |
| きょういくしんりがくけんきゅうほう | ||
| Research Methods in Educational Psychology | ||
| 受講対象学生 |
学部(学士課程) : 2年次 期生 学校教育コース教育心理学専攻生対象 (教育学専攻の学生は,科目名が「教育学研究法」の方を受講ください) |
|
| 卒業要件の種別 | 選択必修 |
|
| 授業科目名 | コミュニケーション論 | |
| こみゅにけーしょんろん | ||
| Communication Practice | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | educ-scho-SCHO1761-001
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
通年 通年集中で行う。集中講義の日程についてはMoodleからの連絡や学務の掲示に注意しておくこと |
|
| 開講時間 |
通年集中 |
|
| 授業形態 |
* 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | 対面 | |
| 担当教員 | 瀬戸美奈子 | |
| SETO Minako | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 大学での学習においては、学習者がグループで活動を行うことがあり、その際には一定のコミュニケーション力を求められることも多い。そこで、本授業では受講生のコミュニケーション力育成を目指す。 またコミュニケーション力を育成する方法についても習得を目指したい。 |
|---|---|
| 学修の目的 | コミュニケーションを分析する方法を学び、自己のコミュニケーション能力を高めソーシャルスキルトレーニングの理解と実践ができるようになる。 |
| 学修の到達目標 | コミュニケーションの分析とグループコミュニケーション力の獲得。そして、それを支援するスキルの獲得。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | グループでの活動における関与の度合いと授業内で出されるレポート。欠席は認められない。 |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
問題提示型PBL(事例シナリオ活用含) プロジェクト型PBL グループ学習の要素を加えた授業 Moodleを活用する授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
| 授業改善の工夫 | 教員から一方的に授業を行うのではなく、実際の活動を通して自発的に学習を行うPBL型授業で進めていく。 |
| 教科書 | 適宜講義中に紹介する。 |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 担当教員が研究室に在室の際に随時対応する |
| 受講要件 | 特になし |
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | |
| その他 | 特になし |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | グループコミュニケーションの実習と省察 |
|---|---|
| Key Word(s) | Communication, Social Skill Training(SST) |
| 学修内容 | 第1時 授業方法,学習目標,成績評価方法などの説明。グループ分け。 第2時 コミュニケーションの場づくり(「安心できる場」をつくるとは) 第3時 ソーシャルスキルという考え方について 第4時 コミュニケーションにおける課題とその支援 第5時 コミュニケーションにおけるチャンネル(言語的・非言語的コミュニケーション) 第6時 コミュニケーションとグループダイナミクス 第7時 コミュニケーション活動(話す①:「話している」ということを伝える) 第8時 コミュニケーション活動(話す②:正確な情報の伝達) 第9時 コミュニケーション活動(聴く①:「受容」の態度を示すには) 第10時 コミュニケーション活動(アサーション:頼み事をする・頼み事を断る) 第11時 コミュニケーション活動(感情マネジメント:自分の感情に気づく) 第12時 コミュニケーション活動の授業案作成 第13時 授業案の発表・実施(第1グループ) 第14時 授業案の発表・実施(第2グループ) 第15時 授業の総括 |
| 事前・事後学修の内容 | 本授業では、コミュニケーション力に関する様々な活動を行うが、それらの活動をただ行うのではなく、省察を行いながら進めていく予定である。それらの省察については、授業時間外に求められることもある。また、コミュニケーション力支援の方法についても実際に自ら作成してもらう可能性があり、それらについても課題として求められる。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |