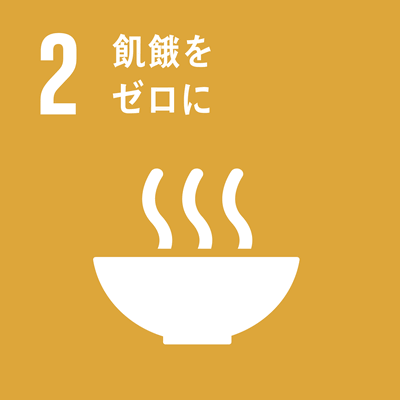シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2021 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 生物資源学研究科(博士前期課程)生物圏生命科学専攻 | |
| 受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次, 2年次 |
|
| 選択・必修 | 選択必修 |
|
| 授業科目名 | 浅海増殖学特論 | |
| せんかいぞうしょくがくとくろん | ||
| Advanced Study in Shallow Sea Aquaculture | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | BIOR-Life-5371-004
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期 |
|
| 開講時間 |
水曜日 1, 2時限 都合により変更となる場合あり |
|
| 授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 筒井 直昭(生物資源学研究科生物圏生命科学専攻) | |
| TSUTSUI, Naoaki | ||
| 実務経験のある教員 | 担当する筒井直昭准教授は国立研究開発法人国際農林水産業研究センターでの勤務経験を有する。 | |
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 漁業は世界中の人々に食料、雇用、レクリエーション、貿易、経済的幸福などを現在~将来にわたって提供すると考えられる。 特に水産養殖は、食料生産産業として最も急速に発展している分野であり、その役割は年々重要になってきている。 養殖を安定化・高度化していくために必要な原理や技術について紹介し、議論する。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 現在までに確立されている種苗生産手法や、今後の発展・応用が期待される技術などについて幅広い知識を得る。 |
| 学修の到達目標 | 種苗生産の技術やそれらの運用について、生物学、生理学的な知見に基づいて理解できるようになる。 水産養殖の将来性について自ら考えられるようになる。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 課題内容のまとめ方と発表方法(40%)、討論の内容や取組姿勢等(60%)。 |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 教員と学生、学生相互のやり取りの一部が英語で進められる授業 |
| 授業改善の工夫 | 討論が活発になるよう、学生の要望を適宜取り入れて改善していく。 |
| 教科書 | 適宜資料を配布する。 |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 12:10~12:50@627室(火曜日以外は連絡要) |
| 受講要件 | |
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 浅海域、水産増養殖、種苗生産、有用魚介類、生物餌料 |
|---|---|
| Key Word(s) | Shallow Waters, Aquaculture, Seedling Production, Aquatic Animals, Live foods |
| 学修内容 | 下記の内容に関する教科書、専門書、文献等を読み、解説する。 順番は状況に応じて変更する場合がある。 1.生体制御の基礎 2.水圏生物の内分泌器官 3.水圏生物にみられるホルモン(脊椎動物1) 4.水圏生物にみられるホルモン(脊椎動物1) 5.水圏生物にみられるホルモン(節足動物) 6.水圏生物にみられるホルモン(軟体動物・棘皮動物) 7.生殖腺の発達(魚類) 8.生殖線の発達とホルモン(魚類) 9.生殖腺の発達(介類) 10.生殖線の発達とホルモン(介類) 11.水圏生物の浸透圧調節とホルモン 12.水圏生物のストレス応答とホルモン 13.餌料生物の利活用 14.多様な養殖手法 15.ゲノム情報を用いた育種や親子判定 |
| 事前・事後学修の内容 | 講義で興味を持った内容や疑問に感じた内容に関して、成書や解説書、事業報告書などを用いて事後学習を行う。 論文調査・発表においては、事前準備に2時間、復習に2時間を必要とする。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |