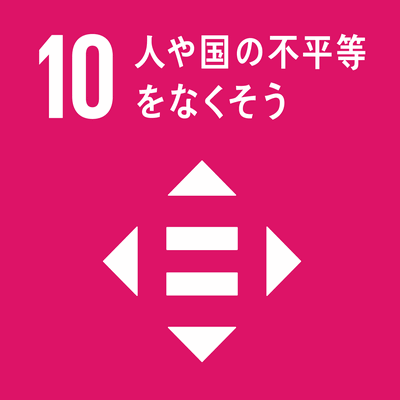シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2021 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文学部文化学科 | |
| 受講対象学生 |
2012年度以降入学生用(文化) 学部(学士課程) : 2年次, 3年次, 4年次 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | アメリカの民族と文化A | |
| あめりかのみんぞくとぶんかえー | ||
| Ethnology of America A | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | humn-cult2140-026
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期 |
|
| 開講時間 |
火曜日 3, 4時限 |
|
| 授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 立川陽仁(人文学部文化学科) | |
| TACHIKAWA, Akihito | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 南北アメリカが多民族国家になった背景としての歴史と現状を理解する。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 南北アメリカの民族の概況を歴史的に理解する。 |
| 学修の到達目標 | ・ラテンアメリカ、アメリカ合衆国、カナダという3つの地域ごとに、民族の歴史と現状が違う点、および共通する点を理解する。 ・上記の相違点および共通点の理由である植民地主義について理解を深めることができる。 ・民族集団が一枚岩的ではなく、じつは内実が複雑な構成になっていることを理解する。 ・文化と呼ばれるものの不安定さ、操作性を理解する。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 授業時間内に小テストないしレポートを課す予定。 |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 | |
| 授業改善の工夫 | |
| 教科書 | なし。 |
| 参考書 | 授業中に紹介。 |
| オフィスアワー | 木曜7から8時限以後。ただし事前にアポをとること。 |
| 受講要件 | とくになし。 |
| 予め履修が望ましい科目 | 教養教育の文化人類学AB、専門科目の文化人類学概論ABを事前にあるいは同時に履修していることが望ましい。 |
| 発展科目 | アメリカの民族と文化演習(A~D) |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 南北アメリカの多民族性の歴史と現状の理解。 |
|---|---|
| Key Word(s) | understanding of the diversity and history of ethnic issues of the Americas |
| 学修内容 | 講義は 1)ラテンアメリカ 2)カナダ 3)アメリカ(各5回程度) の順に、歴史と現代の民族状況、文化について概説。 歴史は、歴史学でいうところの歴史というより、いかにしてそれぞれの国家で多民族性が培われていったかを概説するもの。 現代のトピックとしては、ラテンアメリカでは「音楽」や「インカ帝国と文化遺産」、カナダでは「日系カナダ人」や「カナダのフランス系」、アメリカでは「現代の結婚」などがある。 |
| 事前・事後学修の内容 | 本講義では、南北アメリカの多民族性構築の歴史と現在の文化のいくつかが説明されます。歴史のパートでは、あらかじめレジュメが配られ、重要な点が括弧抜きになっています。また、だいたいにおいて、講義の終わりには、次回講義のトピックが発表されます。 これらをふまえ、事前学修と事後学修では以下のことを求めます。 事前学修: チャート式レジュメがある場合には、括弧内に何が入るかを吟味し、場合によっては文献などで調べておくこと。レジュメがない場合には、次回テーマについて予習しておくこと。 事後学修: 講義内容をもとに、講義で紹介された文献や映画、動画などにあたり、説明された内容を確認しておくこと。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |