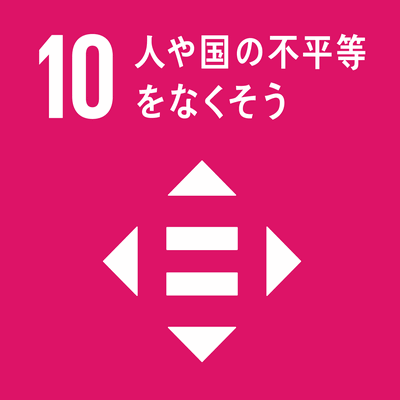シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2021 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 教養教育・教養統合科目・地域理解・日本理解 | |
| 受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 |
|
| 授業科目名 | 日本国憲法 | |
| にほんこくけんぽう | ||
| Constitutional Law of Japan | ||
| 授業テーマ | 教育の法と人権 | |
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | libr-comp-LAWS1121-002
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 分野 | 社会 (2014年度(平成26年度)以前入学生対象) | |
| 開講学期 |
前期 |
|
| 開講時間 |
金曜日 5, 6時限 |
|
| 授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 中岡 淳(非常勤講師) | |
| NAKAOKA Jun | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 教職課程の一環として「日本国憲法」を受講する学生が多いことを念頭に、この授業では、憲法のなかでも教育に関わる個人の基本的人権や国の統治の仕組みを中心に講義を行う。前半(第2回~第6回)は、教育基本法や学校教育法など教育に関わる法がどのような機関によって作られ、その機関が憲法上どのような位置づけにあるのかを学ぶ。後半(第7回~第14回)は、教育のあり方をめぐって生じる人権問題について検討する。その際、実際の裁判例や架空のケースを通じて、受講者の皆さんが事件の当事者や弁護士であったなら、どのような判断を下すかを考えもらう。 |
|---|---|
| 学修の目的 | ①日本国憲法というテクストの基本原理やその背景にある歴史や思想を知る。 ②将来、学校の教員や公務員になったときに、あなたは国家権力の行使の担い手として、憲法の理念や国民の基本的人権に配慮しなければならなくなる。その際に、憲法が、学校の教員や公務員に、どの程度の権力の行使を許し、どのような場合に、その権限の行使が憲法違反となり得るのかを理解する。 ③法律の条文に限らず、新聞や小説、会議の資料など、社会人として恥ずかしくない程度の基礎的なテクストの読解力を身に付ける。 |
| 学修の到達目標 | ①日本国憲法の基本的な考え方について適切に説明できるようになること。 ②難解なテクストであっても、自分の力で読み解く能力が身についていること。 ③日常生活で出会う様々な問題に関して、その時々の感情にとらわれず、客観的かつ論理的に考えられるようになること。また、それを文章で適切に表現できるようになること。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 授業内で実施する小レポート(小テスト)と学期末に行う筆記試験の成績を評価基準とする。 |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
| 授業改善の工夫 | 受講者の要望や理解度に合わせて授業の進行を調整する。 |
| 教科書 | ①西原博史・斎藤一久『教職課程のための憲法入門〔第2版〕』(弘文堂、2019年) ②上田健介ほか『憲法判例50! START UP〔第2版〕』(有斐閣、2020年) |
| 参考書 | 佐藤幸治『日本国憲法論〔第2版〕』(成文堂、2020年) その他、学習に有用な教材や参考資料については授業で適宜紹介する。 |
| オフィスアワー | 質問等については基本的に授業後か連絡先に記載のメールにて受け付ける。 |
| 受講要件 | 特になし。 |
| 予め履修が望ましい科目 | 特になし。 |
| 発展科目 | 憲法を更に深く学びたい方は、人文学部法律経済学科・社会科学科で開講される、内野広大先生の「憲法」および「憲法制度論」の受講を勧める。 |
| その他 |
①教科書2冊は毎回持参すること。六法を購入する必要はない。 ②初回を除き、レジュメや追加資料は三重大学のMoodel上に掲載する。 ③ぼーっと授業を聞いていても意味がない。教員の話すことを自分のことばでメモること。 ④私語等、周囲に迷惑を掛ける受講生に対しては、試験結果からの減点や試験の受験を認めない等の措置を講ずることがあるので、注意すること。 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 憲法、権力分立、基本的人権、教育 |
|---|---|
| Key Word(s) | Constitution, Separation of Powers, The Fundamental Human Rights, Education |
| 学修内容 | 第1回 憲法とは何か 第1部 教育の法をつくるシステムと国の統治の仕組み 第2回 国民が主権を持つことの意味 第3回 議院内閣制における権力分立 第4回 立法権と教育関係法令 第5回 日本の司法制度と違憲審査権 第6回 日本の安全保障体制と憲法9条 第2部 教育に関わる個人の基本的人権 第7回 学校における生徒の幸福追求と校則問題 第8回 教育現場における思想及び良心の自由 第9回 教育現場における信教の自由と政教分離 第10回 教育現場における政治活動の自由 第11回 教育を受ける権利と家族の権限 第12回 教育を受ける権利と教師の権限 第13回 学問の自由と大学の自治 第14回 教育現場における平等とマイノリティの保護 第15回 これまでの授業の総括と発展問題の検討 ※なお、素材とする各テーマは、時事的な出来事や講義の進行具合などにあわせて変更する場合があります。 |
| 事前・事後学修の内容 | 【事前学習の内容】 ①次回授業の予習範囲をMoodleのコース上で確認し、教科書の該当ページを読む。 ②Moodleのコース上に掲載される講義動画を視聴し、レジュメの空欄を埋める。 【事後学習の内容】 ①授業を踏まえてレジュメや参考資料を読み直し、学んだ知識を整理する。 ②各回毎にMoodleのコース上に設定された練習問題を解き、期末試験の対策を行う。 ③授業内で実施した小レポートが返却された場合は、再度、教員の示した小レポートに対する講評や評価基準を踏まえて問題を解き直す。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |