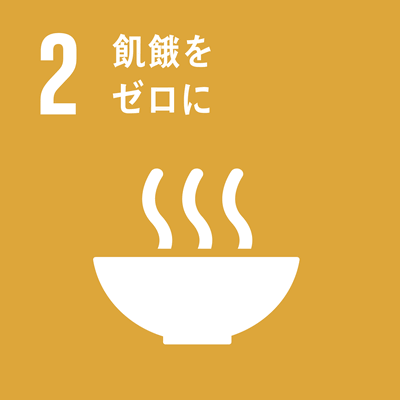シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2021 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 生物資源学部 | |
| 受講対象学生 |
共生環境学科・農業土木学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 |
|
| 選択・必修 | 必修 |
|
| 授業科目名 | フィールドサイエンス実習 | |
| ふぃーるどさいえんすじっしゅう | ||
| Farm practice | ||
| 単位数 | 1 単位 | |
| ナンバリングコード | BIOR-Envi-2334-001
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期 |
|
| 開講時間 |
木曜日 5, 6, 7時限 |
|
| 授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | FSC農場 | |
| 担当教員 | ○渡辺晋生(生物資源学部共生環境学科),加治佐隆光(生物資源学部共生環境学科),近藤雅秋(生物資源学部共生環境学科)、奥田均(生物資源学部附帯施設農場),三島隆(生物資源学部附帯施設農場),長菅輝義(生物資源学部附帯施設農場) | |
| ○WATANABE Kunio, KAJISA, Takamitsu, KONDO, Masaaki, OKUDA, Hitoshi, MISHIMA, Takashi, NAGASUGA, Teruyoshi | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 農作物の生育に応じた栽培管理や収穫物の調整・加工等の技術及び農機具の操作法について体験学習する。 |
|---|---|
| 学修の目的 | イネやムギそして野菜・果樹などの作物栽培における、種まき・収穫・出荷・肥培管理・雑草管理など主要な作業を行う。これによって各種農機具の適正な使用法あるいは精度のよい高能率の作業方法等を自らの手で学び究める。 |
| 学修の到達目標 | イネやムギそして野菜・果樹などの作物栽培における、種まき・収穫・出荷・肥培管理・雑草管理など主要な作業に関する一般的な基礎知識、並びに各種農機具の安全な操作法を習得し、地域課題に対応する基礎的知見を涵養する。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 毎回の実習状況とレポートによる |
| 授業の方法 | 実習 |
| 授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 地域理解・地域交流の要素を加えた授業 |
| 授業改善の工夫 | |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 代表教員 渡辺:kunio@bio へ連絡してください。 |
| 受講要件 | 実習内容上、原則として欠席をみとめない |
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 水稲、野菜、果樹、作物栽培、肥培管理、農機具、水田、農地 |
|---|---|
| Key Word(s) | crop, horticulture, agricultural instruments, paddy field, arable field |
| 学修内容 | 1.ガイダンス・育苗 2.ミニトマトの定植 3.水稲の移植 4.養液栽培(基礎Ⅰ) 5.タマネギの収穫 6.農地の理解 7.水資源・用水の供給 8.養液栽培(基礎Ⅱ) 9.刈り払い機の安全操作 10.水資源・用水の処理 11.亜熱帯果樹の管理 12.養液栽培(基礎Ⅲ) 13.トラクターの操作法・ミニトマトの栽培管理 14.水稲の生育調査 15.ミニトマトの収穫 |
| 事前・事後学修の内容 | 事前:Moodleで各回の予習内容を確認 事後:各回の実習についてのレポート作成 |
| 事前学修の時間:60分/回 事後学修の時間:120分/回 |