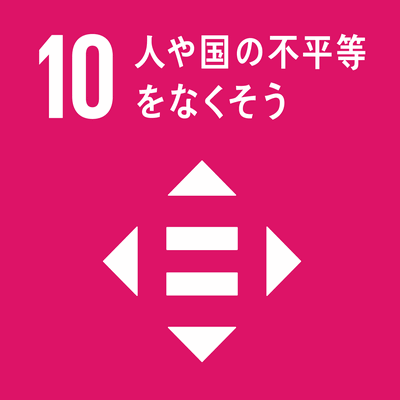シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2020 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文学部法律経済学科・社会科学科 | |
| 受講対象学生 |
法律経済学科専用 学部(学士課程) : 2年次, 3年次, 4年次 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | 行政法総論 | |
| ぎょうせいほうそうろん | ||
| Administrative Law | ||
| 単位数 | 4 単位 | |
| ナンバリングコード | humn-laec2210-015
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
火曜日 3, 4時限; 金曜日 5, 6時限 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 前田 定孝(人文学部法律経済学科) | |
| MAEDA Sadataka | ||
| SDGsの目標 |
|
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 日本国憲法に基づいて、国民との関係で行政権はどのように位置づけられているのか。「法治主義って何だ?」。行政が果たすべき役割、その民主主義的な行政統制のありかた、その権限行使に対する国民主権的な統制のあり方について、先人たちがつくりあげてきた理論体系を一瞥しつつ、今後の未来志向的な「行政法というものの考え方」をともに考える。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 行政法総論の体系を学ぶことで、国家権力に対する民主主義的統制とその権限濫用統制の法理について、その歴史的形成過程とその現段階における理論の姿を概観する。そのことを通じて、「国家」とは何か、社会に生きる私たちとどのような関係にあるのか、私たちは将来にわたってどのような国家・政府像を描き、主体者としてどのようにかかわっていくべきなのか。そして国民が、そのような国家を〈基本的人権〉を守らせるためにコントロールするための法のあり方を考える機会とする。 |
| 学修の到達目標 | 国家・行政とは、国民(人民)が憲法制定を通じて創りだしたものである。そこでは、国民は、主権者として創出した法律を通じて、国家権力にそのなすべき役務の遂行を命じる。そこでは、国家は、あくまでも国民の幸福の追求に資するものでなければならず、国家がその道を大小なりとも踏み外したときには、何らかのかたちで立法上または司法上、その暴走が統制されなければならない。すなわち、国家とは、権力者がその都合で権力的な行為を一方的に「粛々と」あるいは「淡々と」執行するようなものではないなずなのである。 そこでは、国民が「国会における代表者を通じて制定した法律を通じて行政に対してした権限配分と、権利保護過程を通じた救済システムという2つの次元が問題となる。その全体像を把握することによって、国民・住民と国家権力の関係の適切なあり方について考えることができ、さらにその統制法理をみずから創造的に考えることができるようになる。そのことを通じて、将来の主権者としての資質を身につけることができる。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 中間レポートおよび期末レポートによって評価する。 |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
地域理解・地域交流の要素を加えた授業 キャリア教育の要素を加えた授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
| 授業改善の工夫 | 受講生のみなさんの質問や意見、問題関心を反映させて、講義を作り上げたい。 |
| 教科書 | レジュメを配布する |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 第1回目の授業時に情報提供する。 |
| 受講要件 | 特になし。 |
| 予め履修が望ましい科目 | 特になし。 |
| 発展科目 | 特になし。 |
| その他 | 特になし。 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 行政法総論 |
|---|---|
| Key Word(s) | Administrative Law, remedy, Adjudication, Rule making |
| 学修内容 | 現代における国民生活と行政、および法の関係は、大きく変動しつつある。なかでも国レベルで重要な行政法規の制定・改正が相次ぐ一方で、地方自治体におけるさまざまなとりくみも相次いでいる。そこでは、これまで政府が実施してきた活動を民間組織に委ねる傾向も指摘される。その一方で、裁判においても、行政の活動を通じて実現される国民の人権または権利をめぐって次々と重要な判決例が出されている。そしてこれらの展開は、都市開発、環境、社会保障、教育など、あらゆる分野におよんでいる。 それでは、国民は、なにを意図して〈行政〉などというものをつくりだしたのであろうか。また、そこで法律を通じて担わせられる行政上の責務とは、国民がほんとうに意図したとおりに果たされているのであろうか。果たされていないとしたら、どのようにして是正されるのであろうか。 本講義では、これらの答えを自分たちなりに見いだそうと、あえて果敢にとりくむものである。とりわけ、行政情報や不服審査などに関連して、新しい制度が年々誕生するなかで、かかるツールも駆使しつつ、国民・住民の権利実現のために行政は何ができるのか、何をすべきであるのかなどを、ともに考える機会としたい。 〔授業計画〕 (1/2) 行政と行政法の意義 (3/4) 行政法の基本原理-法治主義 (5/6〉 行政権限の委任――組織法関係 (7/8) 行政活動の法体系――その作用、特殊性、および法関係 (9/10) 行政活動の法体系――その手続的側面と行政過程 (11/12) 民主主義的局面における法治主義(その1 行政計画) (13/14) 民主主義的局面における法治主義(その2 行政立法) (15/16) 民主主義的局面における法治主義(その3 情報公開) (17/18) 権限行使局面における法治主義(その1 行政行為①権限行使) (19/20) 権限行使局面における法治主義(その2 行政行為②効力) (21/22) 権限行使局面における法治主義(その4 行政契約) (23/24) 権限行使局面における法治主義(その5 行政指導) (25/26) 権限行使局面における法治主義(その3 権限行使の前提としての情報収集 (27/28) 権限行使局面における法治主義(その6 義務履行確保と強制) (29/30) レポート解説、まとめ、行政法各論・行政救済法への道筋 |
| 事前・事後学修の内容 | さしあたり参考となる文献として、 市橋克哉他編『アクチュアル行政法 第2版』(法律文化社、2015年) |