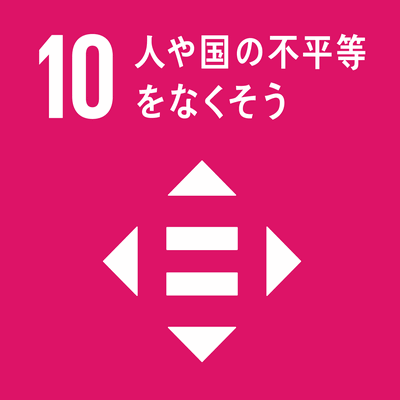シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2020 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文学部法律経済学科・社会科学科 | |
| 受講対象学生 |
法律経済学科専用 学部(学士課程) : 2年次, 3年次, 4年次 2017年度以降入学生用 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | 国際法 | |
| こくさいほう | ||
| Public International Law | ||
| 単位数 | 4 単位 | |
| 受講対象学生 |
法律経済学科専用 学部(学士課程) : 3年次, 4年次 2016年度以前入学生用 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | 国際法総論 | |
| こくさいほうそうろん | ||
| Public International Law | ||
| 単位数 | 4 単位 | |
| ナンバリングコード | humn-laec2210-007
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
月曜日 7, 8, 9, 10時限 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 坂本 一也 | |
| SAKAMOTO, Kazuya | ||
| SDGsの目標 |
|
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 政治的、経済的な利害対立が厳しい国際社会においても、国家間の円滑な関係を維持するために、各国家が従うべき規則―「国際法」―が存在しています。この授業では、この「国際法」の性質や特徴について検討した上で、その具体的な規定内容について考察することにします。授業を通じて、最近のニュースで取り上げられている国際問題などを法的な視点から考える力の涵養を目指します。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 国際法に関する基本的知識を獲得し、具体的な国際問題について法的な視点から考える能力を身に付けること。 |
| 学修の到達目標 | 国際法の性質や特徴を踏まえて、国際法に関わる基本的な知識を習得して、説明できること。 国際問題に関心を持ち、それらを法的な視点から考えるための論理的な思考方法を身につけること。 授業で習得した知識や能力等を用いて、自己の見解を文章によって表現できること。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 筆記試験(定期試験75%)、コメントシート・授業中の発言(25%)で評価します。 |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
| 授業改善の工夫 | レジュメを配布し、一部対話形式(質疑応答)を織り交ぜながら講義形式で授業を進めます。 また、コメントシートの提出を求めることにより、毎回の授業の理解度と共に授業方法の改善点を把握し、講義に生かしたいと考えています。 |
| 教科書 | 教科書は特に指定しません。 国際条約集(いずれの出版社のものでも構いません)は持参してください。 |
| 参考書 | 参考書等については、授業の中で紹介します。 |
| オフィスアワー | 授業終了後に受け付けます。 |
| 受講要件 | 特にありません。 |
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | |
| その他 | 授業中の質疑応答に積極的に関わってください。また、新聞などの国際面に目を通してください。 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 国際社会、主権国家、条約・国際慣習法、領土問題、海洋法、武力紛争・平和 |
|---|---|
| Key Word(s) | International Society, Sovereign States, Treaties/Customary International Law, Conflicts of Territories, Maritime Law, Armed Conflicts/Peace |
| 学修内容 | 第1回 講義ガイダンス(授業の進め方、国際法とはどのような法か) 第2回 国際法の歴史的展開 第3回 国際社会の構造と国際法の特徴① 第4回 国際社会の構造と国際法の特徴② 第5回 国際法の法源(国際慣習法を中心に) 第6回 条約法① 第7回 条約法② 第8回 国際法と国内法の関係 第9回 国際法における主体 第10回 国家の成立から消滅まで(国家の構成要件と国家承認) 第11回 国家の基本的権利義務①(主権平等原則・国内問題不干渉原則) 第12回 国家の基本的権利義務②(国家免除) 第13回 外交・領事関係法 第14回 中間まとめ(国際法における「国家」について) 第15回 国家領域とその機能(領域主権) 第16回 国家領域の取得権原 第17回 日本の領土問題 第18回 海の国際法①(海洋法秩序) 第19回 海の国際法②(海洋権益をめぐる対立) 第20回 空と宇宙の国際法 第21回 国家の国際責任①(成立要件) 第22回 国家の国際責任②(責任追及・解除の方法) 第23回 国際法上の個人の地位①(国籍・外国人) 第24回 国際法上の個人の地位②(難民) 第25回 紛争の平和的解決 第26回 紛争の司法的解決(国際司法裁判所) 第27回 戦争・武力行使の違法化(武力不行使原則) 第28回 自衛権と国連における集団安全保障 第29回 武力紛争法・国際人道法 第30回 総まとめ(国際法とはどのような法か(再考)) |
| 事前・事後学修の内容 | 授業で配布するプリントに事前に目を通しておいてください。また、前回の授業内容を次の授業の初めに確認しますので、復習をしてください。 具体的な予習の方法や範囲については毎回の授業で案内します。 また、授業で取り上げる判決や関連する国際問題については書籍、インターネットなどを参照して事前・事後学習をしておいてください。 |