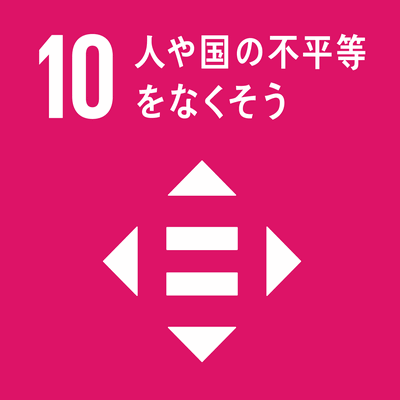シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2020 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文学部文化学科 | |
| 受講対象学生 |
2012年度以降入学生用(文化) 学部(学士課程) : 2年次, 3年次, 4年次 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | アメリカの思想B | |
| あめりかのしそうびー | ||
| American Philosophy B | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | humn-cult2140-003
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
水曜日 3, 4時限 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 薄井 尚樹(人文学部) | |
| USUI, Naoki | ||
| SDGsの目標 |
|
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 今世紀に入り,私たちがしばしば気づくことのないとされる「潜在的態度」あるいは「潜在バイアス」についての研究が進展してきました.本講義では,その研究を紹介するとともに,「潜在的態度は「本当の私」なのか」,「潜在的態度の道徳的責任をどう考えるべきか」,「潜在的態度は他の心的状態とどのように異なるのか」といった,哲学的なトピックを扱います. |
|---|---|
| 学修の目的 | 1. 潜在的態度をめぐる経験的研究の成果を理解できる 2. 潜在的態度からどのような哲学的問題が生じるかを理解できる |
| 学修の到達目標 | 1. あるトピックについての論争を考察することで,相手の主張を批判的に吟味できる. 2. 多様な哲学的立場を概観することで,複数の立場を系統立てて比較できる. |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 期末試験70%,レスポンスペーパー30% |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
| 授業改善の工夫 | ・毎回の講義では,質問・要望欄を設けたレスポンスペーパーを配布する.学生からの質問には次回の講義の冒頭で回答し,指摘された要望を取り入れることで柔軟な内容改善を図る. ・一方的な講義形態にならないように、板書を交えつつ学生との対話を図る. ・全講義を通じて数回コンセプトマップを学生に作成させる機会を設ける.それを通じて学生に知識の整理をおこなってもらい,同時に学生たちの理解状況を確認する. ・哲学には難解な語句や抽象的な概念が伴いがちだが,毎回の講義タイトルも含め,平易な言葉で講義をおこなう. |
| 教科書 | Madva, A., & Beeghly, E. (Eds.) (2020). An Introduction to Implicit Bias: Knowledge, Justice, and the Social Mind. Routledge. (ただし講義中に用いることはありませんし、受講者が読んでおく必要もありません。講義と配布するレジュメだけで完結します.) |
| 参考書 | 講義のなかで適宜,紹介します. |
| オフィスアワー | 毎週水曜日 12:00〜13:00 薄井研究室(人文学部) |
| 受講要件 | 講義を受けるにあたって,予備知識は必要ありません. |
| 予め履修が望ましい科目 | 講義を受けるにあたって,予備知識は必要ありません. |
| 発展科目 | アメリカの思想・アメリカ思想演習 |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 潜在的態度,道徳的責任 |
|---|---|
| Key Word(s) | implicit attitudes, moral responsibility |
| 学修内容 | 第1回:イントロダクション 第2回:潜在バイアスのしくみ 第3回:潜在バイアスと身体化 第4回:バイアスについての懐疑論 第5回:バイアスと知識 第6回:バイアスと知覚 第7回:認識的不正義と潜在バイアス 第8回:前半のコンセプトマップの作成 第9回:ステレオタイプ脅威 第10回:潜在バイアスの道徳的責任 第11回:認識的責任と潜在バイアス 第12回:不正義の説明 第13回:個体的介入と構造的介入 第14回:後半のコンセプトマップの作成 第15回:講義全体のまとめ ※ただし受講者の関心や理解度に応じて内容を部分的に変更することがあります. |
| 事前・事後学修の内容 | ・「哲学」というと難解なイメージを持ってしまうかもしれませんが,哲学者たちが考え,悩んできたことは,私たちが日常的に直面する問題と変わりません.講義の予習のために資料を配布しますが,それを読むときには、言葉の難しさに惑わされず,自分がふだん思っていることにつなげて理解するように意識しましょう. ・ただレジュメを読むだけでなく,講義中に自分で考えたことをレジュメに書き込むようにしましょう.復習の際に読み返してみて疑問に思ったことは,講義中に質問の時間を設けますので,そのときに質問するか,講義の最後に配布するレスポンスペーパーの質問欄に記入して提出してください. |