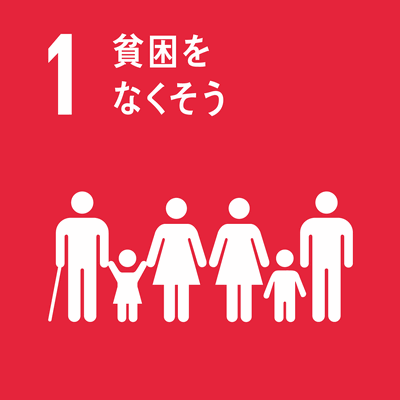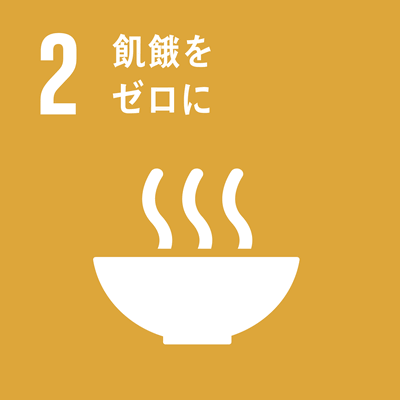シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2020 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 生物資源学部 | |
| 受講対象学生 |
全学科・全教育コース 学部(学士課程) : 3年次 |
|
| 選択・必修 | 必修 国際・地域資源学、海洋生物資源学教育コース指定科目 |
|
| 授業科目名 | 水産経済学 | |
| すいさんけいざいがく | ||
| Fisheries Economics | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | BIOR-Reso-2331-010
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期 |
|
| 開講時間 |
金曜日 3, 4時限 |
|
| 開講場所 | 後で通知する | |
| 担当教員 | 常 清秀(生物資源学部資源循環学科) | |
| jyou seisyu | ||
| 実務経験のある教員 | 授業担当者は、長年に渡り、漁村地域をフィールドとして、漁業・養殖業の生産から流通販売に至るまで幅広い実態調査を行い、多くの関連業績を有する。 | |
| SDGsの目標 |
|
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 海洋資源の適正利用と適正管理、および持続可能な生産・流通システムのあり方について、経済学の視点から学ぶ。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 漁業の多面的機能を理解したうえ、漁業が産業とする特性、海洋資源が商品とする特性を把握し、これらの資源を対象とする産業分野での経済活動(=水産経済学分野)でをである水産動植物の経済的利用と資源管理の仕組み、現存の生産・との関係を経済学的な視点から理解し、水産経済学の分野で生じた諸現象に対する考察力を高めることを目的としている。 |
| 学修の到達目標 | 水産資源は自律更新的資源の典型であると同時に、強い資源の制約を持っている。こうした特徴を持つ産業(=漁業)を正しく理解し、水産業界で生じた諸現象を専門知識に基づき、ある程度説明できるようになること。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 受講姿勢と期末試験 |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 |
| 授業改善の工夫 | ①授業アンケートの結果を踏まえて、授業改善をすること。 ②定期的に授業内容に対する「理解度チェック」(チェックシートを用いて)を行うこと。 ③学生とのコミュニケーションをとれるように、授業中、なるべく質疑の時間を増やすように考慮していること。 |
| 教科書 | 教科書なし。自分で作成した講義資料をPDFファイル形式でMoodle上で配布する。 |
| 参考書 | ・大海原宏・長谷川彰・志村賢男・八木庸夫・高山隆三編著「現代水産経済論」北斗書房(1982) ・桜本和美著「漁業管理のABCーTAC制がよく分かる本ー」成山堂(1998) ・廣吉勝治・佐野雅昭編著『ポイント整理で学ぶ水産経済』北斗書房(2008) |
| オフィスアワー | 毎週金曜日12:00-13:00 場所:341号室 事前予約が必要。 |
| 受講要件 | 特になし |
| 予め履修が望ましい科目 | 農業経済学、農業経営学、フードシステム論を履修することが望ましい。 |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 漁業資本、漁業権、排他的経済水域、漁協、漁業所得、水産物の需給、水産物の流通システム、市場流通、市場外流通 |
|---|---|
| Key Word(s) | Fishery capital, Fishery Right,Exclusive economic zone, Fishery cooperative association, Fishery income, Supply and demand of seafood, Seafood system, distribution in wholesale market , outside market distribution. |
| 学修内容 | はじめに 水産業の特徴と水産経済学とは(初回講義) 第一部 水産物がどのように生産されているのか?(計5回) 漁業の種類・生産方法と漁法別の生産性・生産組織・仕組み・ルールなど 第二部 水産物がどういう仕組みで流通・販売されているのか?(計4回) 流通の仕組み・制度・取引方法・市場規模・市場動向・消費者のニーズなど 第三部 漁業経営と漁業就業(計2回) 経営組織別(家族経営・組合自営・会社経営等)の特徴・経営分析・賃金制度・漁業就業・諸保険制度など 第四部 漁業の国際関係と環境問題(計3回) (1)漁業の国際関係・国連海洋法条約・地域漁業管理機関・漁業協定(日韓・日中・日ロ・日米) (2)漁業・水産業をめぐる環境問題 期末試験(第16回目講義) |
| 事前・事後学修の内容 | 事前学修 ・関連統計資料を用いて、事前に現状把握できるように適宜に課題を与える。 ・企業のHP情報を活用し、企業展開の特徴など事前に調べる。 事後学修 授業で学んだことを日常生活の中で考察し、レポートするなど。 |