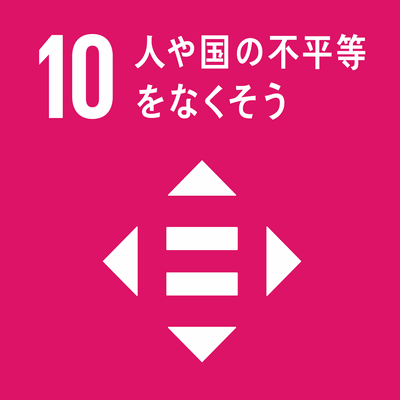シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文社会科学研究科(修士課程)地域文化論専攻 | |
| 受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次, 2年次 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | 文化人類学特講 | |
| ぶんかじんるいがくとっこう | ||
| Special Lecture on Cultural Anthropology | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | HUCLTR4
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期 |
|
| 開講時間 |
|
|
| 授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 立川 陽仁(人文学部文化学科) | |
| TACHIKAWA, Akihito | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | グローバリズム、近代化などに関する人類学的な文献を読み、上記テーマについての理解を深める。 |
|---|---|
| 学修の目的 | グローバリズムや近代資本主義システムの世界的な浸透について、各事例にもとづいた理解を得ることができる。 |
| 学修の到達目標 | グローバリズムや近代資本主義システムについて、世間でいわれているような一枚岩的な評価だけでなく、実態の多様性を批判的に理解する。とくに各地域が近代やグローバリズムを受け入れる際の、主体的な動きや戦略を理解する。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 英語テキストを使用した場合には、履修者には分担箇所についての全訳を課す。 日本語テキストを使用した場合には、分担箇所のレジュメを作成する。 この作業で評価する。 |
| 授業の方法 | 講義 演習 |
| 授業の特徴 |
プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) 教員と学生のやり取りは日本語でも、英語による論文や教材の講読を含んだ授業 |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | |
| 教科書 | E. Wolf, Europe and the People without Historyを考えているが、場合によっては以下の日本語文献を利用する可能性もある。 『日常人類学宣言!』松田素二 『開発の人類学』前川啓治 |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 木曜の7~8時限。 |
| 受講要件 | |
| 予め履修が望ましい科目 | 文化人類学および社会学関連の授業 |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 文化人類学理論、フィールドワーク論、グローバリズム、世界システム。 |
|---|---|
| Key Word(s) | theory of cultural anthropology, field work, globalsim, world system |
| 学修内容 | テキストを読み進め、それにもとづいた討論をおこなっていく。 第15回までの毎回、1章ごと進めていく予定。 |
| 事前・事後学修の内容 | 英語テキストを使用する場合は全訳、日本語テキストを使用する場合はレジュメを作成する。 その他の関連する文献については授業中に紹介するので、それも参照することが望ましいし、学生に求められてもいる。 事前学修はテキストの読解あるいはレジュメ作成に、事後学修は講義で紹介された文献を参照することに使う。 |
| 事前学修の時間:210分/回 事後学修の時間:30分/回 |