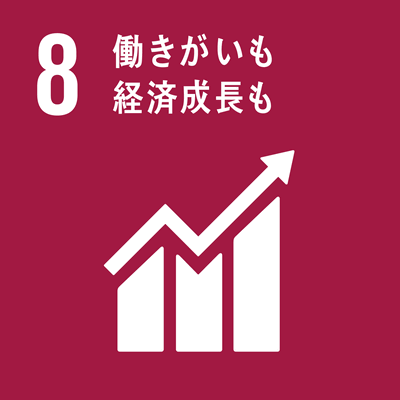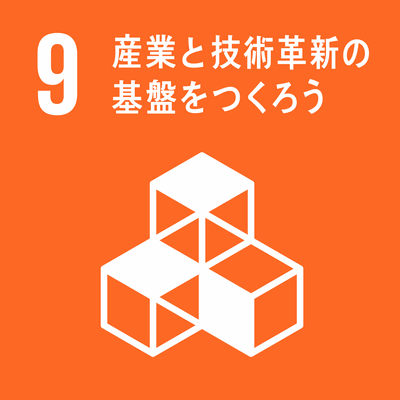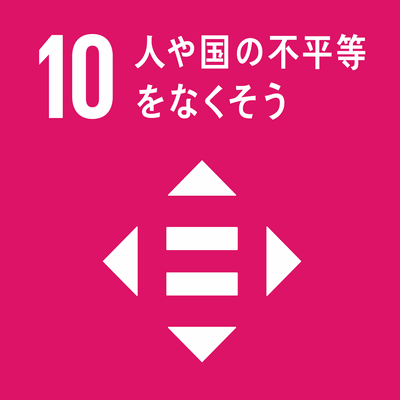シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文学部法律経済学科 | |
| 受講対象学生 |
学部(学士課程) : 2年次, 3年次, 4年次 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | 国際金融論 | |
| こくさいきんゆうろん | ||
| International Money and Finance | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | humn-laec2230-026
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
金曜日 5, 6時限 |
|
| 授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 野崎 哲哉(人文学部) | |
| NOZAKI Tetsuya | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 講義では国際金融の基礎的な理解(国際金融取引の仕組みや国際金融システムの現状と課題等)が深まることを目指すとともに、問題意識を課題意識に発展させられるようにするために、現代的な国際金融の諸問題も取り上げることとする。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 国際金融に関する基礎理論の修得に加えて、日々生起する様々な国際金融の関連事象の背後にはどのような理論的課題があるのか理解できるようになることを目的とする。 |
| 学修の到達目標 | 国際金融に関する基礎的な知識の習得を目的とするとともに、国際金融に関連する今後の課題を考えられる能力の育成を目指したい。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 期末テスト(40%)、レポート(30%)、毎回の講義での意見カード等(30%)で総合的に評価 |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 |
Moodleを活用する授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | 毎回の講義で学生の意見・質問を聞くとともに、理解度を確認するためにリアクションペーパーを活用する。またより理解が深まる視聴覚教材や新聞記事、専門雑誌等の活用を図っていきたい。 |
| 教科書 | 毎回、講義レジュメを配布する。 |
| 参考書 | 講義時に指示する。 |
| オフィスアワー | 火曜日および金曜日の昼休み |
| 受講要件 | 特になし |
| 予め履修が望ましい科目 | 金融論 |
| 発展科目 | 特になし |
| その他 | 国際金融を理解するためには金融に関する基礎的な理解が求められるため、金融論を履修していることが望ましい。 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=19032 |
|---|
| キーワード | 現代経済社会と国際金融の役割 |
|---|---|
| Key Word(s) | The role of international finance in the modern economic society |
| 学修内容 | ☆講義の流れは以下の通り 第1回 講義ガイダンス・国際金融に関するトピックス 第2回 国際金融とは何か~国際金融はなぜ生まれるか?~ 第3回 国際金融を理解するためのポイント 第4回 国際収支について 第5回 貿易金融の仕組み 第6回 外国為替と国際通貨 第7回 為替相場と円高・円安 第8回 現代の国際金融・資本市場 第9回 ドル体制の変遷と現状 第10回 リーマンショック後のアメリカ経済 第11回 ユーロ体制の現状と課題 第12回 新興国の金融問題 第13回 人民元の国際化 第14回 国際金融規制の現状と課題 第15回 講義のまとめ |
| 事前・事後学修の内容 | 毎回、講義内容に関連した学習課題を示すこととしたい。 復習については、毎回配布するレジュメを必ず読み返してくることを求めるとともに、予習については、必要に応じて予習用の別プリントを配布する予定。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |