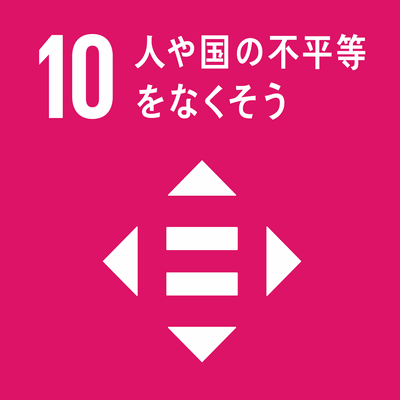シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 教育学部・教科及び教科の指導法に関する科目(A類)・美術 | |
| 科目名 | デザイン | |
| でざいん | ||
| design | ||
| 受講対象学生 |
教育学部, A 類 学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次 大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次, 2年次 〜71 期生 |
|
| 卒業要件の種別 | 選択必修 |
|
| 授業科目名 | 色彩学 | |
| しきさいがく | ||
| Color study | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | educ-arts-ARTS1033-001
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
水曜日 3, 4時限 |
|
| 授業形態 |
* 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | 美術棟2階デザイン教室 | |
| 担当教員 | 岡田博明 | |
| OKADA Hiroaki | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 色彩についての基礎概念を理解するとともに、カラーテキストを使用し、色の伝達、効果を検証し、配色の基礎演習を行う。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 色に関する本質的な理解と表示方法を理解し、目的にあった色を使用できる力を養う。 |
| 学修の到達目標 | 色に関する本質的な理解と表示方法を理解、目的にあった色を使用できる力の獲得。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 出席と総合演習課題の評価 |
| 授業の方法 | 講義 |
| 授業の特徴 | |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | |
| 教科書 | 日本色研「デザインの色彩」 |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 毎週木曜日12:00〜13:00 |
| 受講要件 | 「一部、絵の具を使用するので、指定された授業時間に用意すること(絵の具、筆、筆洗、パレット、雑巾)。絵の具はなんでも良いが不透明アクリル絵の具(アクリルガッシュ)が最も望ましい。 |
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | |
| その他 | この講義は隔年開講なので注意する事。2025年度は開講しない |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 色彩、色彩計画、光、配色、色の意味、色の見え方、色の感じ方、色の機能、 |
|---|---|
| Key Word(s) | Color・Color plan・Light・Put a Color・Meaning of the color・Identification of the color・Feeling of the color・Function of the color |
| 学修内容 | 第1回・ガイダンス/光の本質 第2回・テキスト解説/第1部/色の本質 そのⅠ 第3回・/色の本質 その2 第4回・/色彩の伝達 第5回・/目の生理学 第6回・/無意識的な意味と評価 第7回・/色の対比 第8回・/残像 第9回・/色の感じ方 第10回・/光の散乱による色 第11回・/色の光学的再現 第12回・/混色 第13回・/色の機能/色の効果 第14回・/演習1 第15回・/演習2 |
| 事前・事後学修の内容 | 教科書に指定してある本は実際に色(色紙)を貼っていき完成させる形式の本なので、指定された授業日までに完成させておく事 |
| 事前学修の時間: 事後学修の時間: |