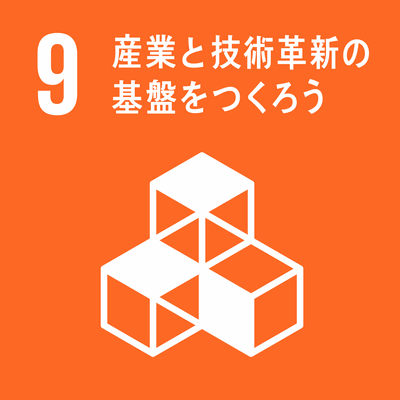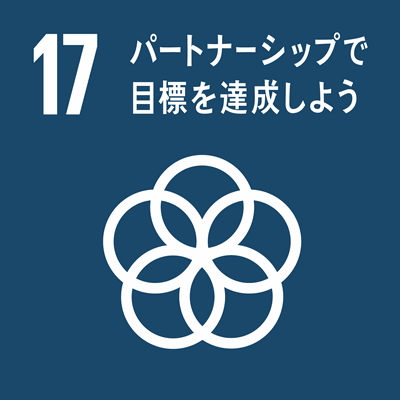シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 教育学部・教科及び教科の指導法に関する科目(A類)・技術 | |
| 科目名 | 技術科教育 | |
| ぎじゅつかきょういく | ||
| Technology Education | ||
| 受講対象学生 |
A 類 学部(学士課程) : 3年次 74 期生 |
|
| 卒業要件の種別 | 必修 技術・ものづくり教育コースの学生は必修です。 |
|
| 授業科目名 | 【遠隔】技術科教育法Ⅲ | |
| ぎじゅつかきょういくほうさん | ||
| Methodology of Technology Education III | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | educ-comn-ENGR2121-003
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期 |
|
| 開講時間 |
月曜日 5, 6時限 複数回の休講、補講がある。日程については、別途相談して、決定する。 |
|
| 授業形態 |
オンライン授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | 学生は、技術棟T-201教室からオンライン授業に参加することを求めることがある。 | |
| 担当教員 | 長谷川元洋(非常勤講師) | |
| HASEGAWA, Motohiro | ||
| ghase@kinjo-u.ac.jp | ||
| 実務経験のある教員 | 授業担当者は、技術の中学校教員として経験が15年間ある。技術教育の情報の分野に関する教育について実践と研究を行ってきた。6年間附属中学校教員として教育実習生を指導した経験を生かした授業を実施する予定である。 | |
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 本授業では,技術科の授業を構想し、計画し、実際に授業を行う力を身につけることを目指す。指導案作成や模擬授業を複数回行い、実践力を身につけるとともに、学生相互に学び合い、互いに力を高めることを目指す。 |
|---|---|
| 学修の目的 | この授業を受講することにより,教育実習において実際に授業を遂行できることをねらいとしている。 |
| 学修の到達目標 | ・学習指導要領に示された技術科教育に係わる教科の目標及び主な内容,全体構造を説明できる。 ・学習指導要領に示された技術科教育に係わる個別の学習内容について指導上の留意点を理解した上で,学習指導案(単元案と本時案)を作成することができる。 ・技術科教育における主な学習指導方法を説明できる。 ・技術科教育における学習評価の考え方を理解した上で,評価を活用した学習支援を構想し,実際に模擬授業において学習評価を生かした授業ができる。 ・技術科教育の背景となる学問領域との関係を理解し,教材研究に活かすことができる。 ・技術科教育における安全教育について説明できる。 ・技術科教育における模擬授業を構想・立案し,実践できる。 ・技術科教育における生徒の認識や思考,学力などの実態を視野に入れて授業設計ができる。 ・技術科教育の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用ができる。 ・技術科教育の教育課程と学習指導案の構造を理解し,具体的な授業を構想した授業設計を行い,学習指導案を作成できる。 ・技術科教育における模擬授業の実施とその振り返りを通して,授業改善の視点を身につけることができる。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 作品(制御プログラムも含む)60%、プレゼンテーション30%、相互評価 10% 計100%。 ただし、3分の2以上の出席であること。 |
| 授業の方法 | 講義 実習 |
| 授業の特徴 |
問題提示型PBL(事例シナリオ活用含) 問題自己設定型PBL プロジェクト型PBL プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 グループ学習の要素を加えた授業 Moodleを活用する授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | Moodleを用いて、学生が相互に議論したり、情報交換したりすることを推奨している。 |
| 教科書 | 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 |
| 参考書 | 中学校技術・家庭科 技術分野の教科書、インターネット上に公開されている資料 |
| オフィスアワー | 授業の前後。その他、電子メール等で相談に応じる。 連絡窓口教員:松本金矢(教育学部教授)matumoto@edu.mie-u.ac.jp |
| 受講要件 | なし |
| 予め履修が望ましい科目 | 技術科教育法Ⅰ,技術科教育法Ⅱ |
| 発展科目 | 技術科教育法Ⅳ |
| その他 | 基本的には、オンライン(リアルタイム型)で実施する。模擬授業等の演習は、学生のみ教室にいて、授業を行うことがある。 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 技術教育、教育法、指導案 |
|---|---|
| Key Word(s) | Technology Education, Teaching Method, Lesson Plan |
| 学修内容 | 第1回 (4/15) <オンライン(リアルタイム型)>この授業の目標、技術分野の目標、資質・能力等について 第2回 (4/22) <オンライン(リアルタイム型)>技術科の授業を通じて生徒に身につけさせたい力の検討、生徒への学び方の指導について、附属中学校の指導案の書式について 第3回 (5/1) (対面)主体的・対話的で深い学び、評価の観点について、学びのルーブリックについて 第4回 (5/13) <オンライン(リアルタイム型)>QFOCUSの構想、主発問の設定、教材研究 第5回 (5/20) <オンライン(リアルタイム型)>指導案の単元目標、単元計画の策定、学びのルーブリックの作成 第6回 (5/27) <オンライン(リアルタイム型)>本時案の作成 第7回 (6/3:休講) 補講日は調整の上、決定する。 本事案、教材の作成、完成 第8回 (6/10) <オンライン(リアルタイム型)> 全体案の書き方 第9回 (6/17) <オンライン(リアルタイム型)>模擬授業(30分× 3名) 第10回 (6/24) <オンライン(リアルタイム型)>模擬授業(30分× 3名) 第11回(7/1) <オンライン(リアルタイム型)>模擬授業(30分× 3名) 第12回 (7/8) <オンライン(リアルタイム型)>情報の技術 (情報モラル) 3つのアクティブラーニング型授業の紹介 第13回 (7/22) <オンライン(リアルタイム型)> 模擬授業(30分× 3名) PBL型授業 第14回 (7/29) <オンライン(リアルタイム型)>模擬授業(30分× 3名) 思考ツール活用型授業 第15回 (8/5) <オンライン(リアルタイム型)>模擬授業(30分× 3名) QFT(質問作り)を活用した授業 *教育実習訪問、小中学校の研究授業の指導等により、休講する可能性がある。補講日は、調整して決定する。 。 |
| 事前・事後学修の内容 | 指導案や教材作成は、授業時間内だけでは、完成できない。1単位あたり45時間の学修が必要であることを踏まえ、事前、事後学修に取り組むこと。 (参考) 指導案、レポート、模擬授業、授業中の個人、グループの取り組みを評価対象とする。 指導案40%, 模擬授業 30%, 授業中の活動 15%, 毎回の授業の振り返り 15% |
| 事前学修の時間:90分/回 事後学修の時間:90分/回 |