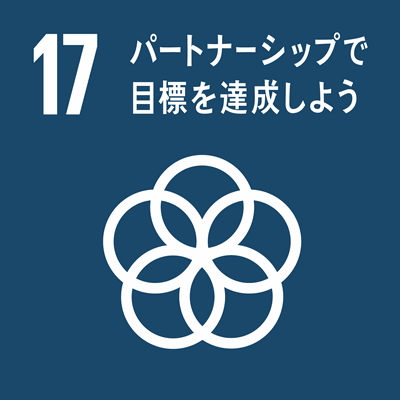シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 共通教育・教養基礎科目 | |
| 受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 |
|
| 授業科目名 | PBL医学・看護学 | |
| ぴーびーえる いがく・かんごがく | ||
| PBL Medical Science and Care | ||
| 授業テーマ | 授業作成で学ぶ生理学 | |
| 単位数 | 2 単位 | |
| 受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 2022年度以前の入学生に対する科目名 |
|
| 授業科目名 | PBL医学・看護学(現代科学) | |
| ぴーびーえる いがく・かんごがく(げんだいかがく) | ||
| PBL Medical Science and Care | ||
| 授業テーマ | 授業作成で学ぶ生理学 | |
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | gedu-libr-MEDN1419-005
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 分野 | 健康・医療・福祉 | |
| 分類・領域 |
教養統合科目・現代科学理解 (2022(令和4)年度〜2015(平成27)年度入学生対象) |
|
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
火曜日 7, 8時限 |
|
| 授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 玉利 健悟(全学共通教育センター) | |
| TAMARI, Kengo | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 本授業は、教員の立場となり、人体の生理学についての授業作成することで、学修をさらに深める授業となっている。生理学の知識は授業時間外に担当教員作成の動画により学修する。そして、授業時間では学修内容を確認した後、もし授業を作成するのであれば、どのような工夫が出来るかを考察する。毎回の考察をまとめ、工夫を作成し、最終回で発表する。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 授業の工夫を考察することにより、知識の定着だけでなく、教員の発想を獲得できる。 大学の授業で不可欠なプレゼンテーション能力も養成する。本授業を履修することで、理系であれば、専門教育の基礎とし、文系であれば、身の回りの健康問題に対応する基礎知識を習得する。 |
| 学修の到達目標 | ・基本的な人体の仕組みを概説できる(C評価) ・人体の仕組みについて概念を理解し、グループで討論できる。(B評価) ・人体の仕組みの授業作成を行い、人体について多角的に論じることができる(A評価) ・人体の仕組みについてまとめ上げ、的確で明解な授業をすることができる(AA評価) A評価以上の学生は3つの能力を向上することを狙っています。①人体に関わる様々なリテラシー。②研究の基本となる計画性と実践力。③コミュニケーションによる課題解決力。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 個別確認テスト10%、グループ確認テスト20% グループ活動の評価20%、作成授業の評価50%、計100%。(合計が60%以上で合格) |
| 授業の方法 | 講義 演習 実技 |
| 授業の特徴 |
問題提示型PBL(事例シナリオ活用含) プロジェクト型PBL 反転授業 プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 グループ学習の要素を加えた授業 Moodleを活用する授業 |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | 人体の仕組みの中でも、身近に感じる項目を中心に授業する。また、グループ演習問題の解答を行うことで、 理系・文系や学科間でも知識の差の少ない成績評価を行う。 |
| 教科書 | 特になし 講義中に資料を配布 |
| 参考書 | 解剖生理学(メディカ出版) 解剖生理学(医学書院) |
| オフィスアワー | 毎週火曜日の12:00~12:45、共通教育1号館310号室 |
| 受講要件 | 理系・文系問わない |
| 予め履修が望ましい科目 | 生物基礎などの生物学を履修していると理解が早い |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 生理学 医学 生命科学 |
|---|---|
| Key Word(s) | Physiology Medicine Life science |
| 学修内容 | 第1回 オリエンテーション 第2回 授業作成の方法 第3回 細胞と細胞小器官 第4回 消化器系 第5回 呼吸器系 第6回 循環器系 第7回 泌尿器系 第8回 内分泌系 第9回 生殖器系 第10回 神経系1 第11回 神経系2 第12回 感覚器系 第13回 免疫・血液系と発表内容決定 第14回 授業作成・発表練習 第15回 総括 |
| 事前・事後学修の内容 | 事前学習:解剖生理学と名の付く教科書を予習すると良い。また、普段から健康、医学、医療に関わる メディアの情報を得る努力をしておくこと。 事後学修:一日の講義で行った知識をもう一度覚え直し、期末試験に対策すると良い。また、Moodleにて 質問を受け付けるので、いつでも疑問に思うことがあれば解決して次の講義に臨むこと。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |