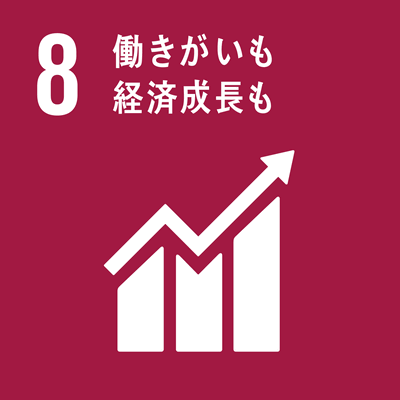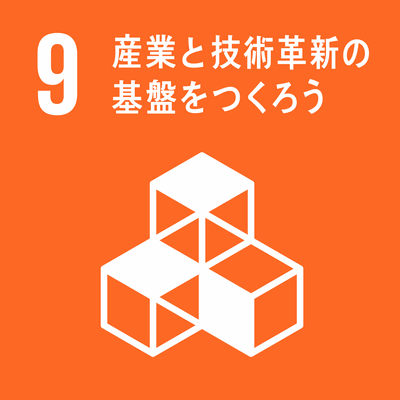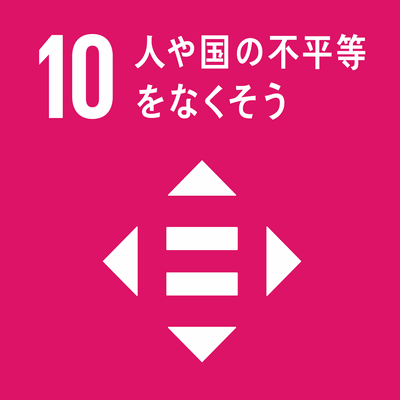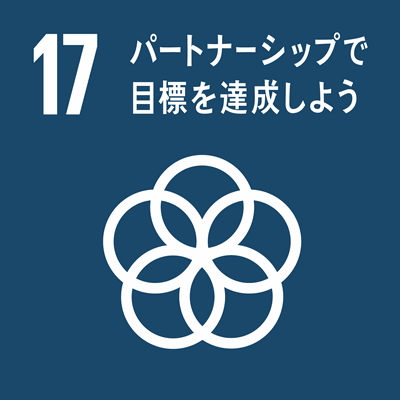シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 人文学部法律経済学科 | |
| 受講対象学生 |
学部(学士課程) : 3年次 |
|
| 選択・必修 | ||
| 授業科目名 | 経済原論演習 | |
| けいざいげんろんえんしゅう | ||
| Seminar in political economics | ||
| 単位数 | 4 単位 | |
| ナンバリングコード | humn-laec3230-010
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
通年 |
|
| 開講時間 |
金曜日 7, 8時限 |
|
| 授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 深井 英喜(人文学部) | |
| FUKAI, Hideki | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | この講義では、講義で学んだ知識をより深めて実際に使えるようになることを目標にして、少人数での輪読や議論そして論文執筆を通した学習を行う。 最終的には、卒業研究の指導まで行う。 |
|---|---|
| 学修の目的 | この演習が目的とするところは、次の3点である。 ・理論経済学の基礎の習得を目指す。 ・理論経済学の考え方を使って現代資本主義社会の諸現象や諸問題について考える、応用力を高める。 ・“論理的思考”や“コミュニケーション力”といった力を高めることを目指す。 |
| 学修の到達目標 | この演習の1つ目の目的は、理論経済学の基礎をしっかりと習得することにある。とは言っても、経済学のテキストにある経済モデルを単にわかった気になったのでは応用力はつかない。この演習では、経済モデルが前提にしている社会の特徴を考察してこれを検討することで、その理論がどのような特徴を持つとともに限界を持っているかを理解することを目標にする。 また、この演習では合宿なども行い、ゼミ生間の議論を行ってもらう。その中で、社会に出る際に必要な諸力(“how to”ではなく、論理的思考やコミュニケーション力)とは何かを自分なりに考えて、その力を高めていくことを目標にする。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 授業参加度100% |
| 授業の方法 | 演習 |
| 授業の特徴 |
グループ学習の要素を加えた授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | |
| 教科書 | 輪読形式が中心になるが、テキストについては参加者との相談の上で決めていく。 |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 私が研究室にいれば、いつでもよい。 |
| 受講要件 | 積極的に演習の活動に参加すること |
| 予め履修が望ましい科目 | 経済原論ないしは近代経済学を事前に履修していることが望ましい |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | 理論経済学 ラディカル派経済学(ケインズ経済学、ポスト・ケインズ経済学、マルクス経済学、制度学派経済学) ちなみに私の研究分野は、福祉国家体制論(特にイギリス)、貧困・社会的排除問題、社会保障論、分配・再分配論、労働市場理論、家族経済学である。 |
|---|---|
| Key Word(s) | Radical Economics Seminar |
| 学修内容 | ● 夏セメスター 理論経済学のテキストの輪読を中心に進め、経済学の基礎的な考え方の習得と定着を目指す。 また、『学生論集』やインゼミ(日本学生経済ゼミナール)に向けてゼミ共通のテーマを設定し、ゼミ内研究会を行っていく。具体的には、テーマに関する著書や論文を探し、その内容をゼミ内に紹介していってもらう。 ● 冬セメスター 『学生論集』やインゼミで設定したテーマに即して、専門書の輪読を中心に進める。夏セメスターで学んだ経済理論の知識を具体的な問題にあてはめて用いることで、理論経済学がもつ意味をより具体的に理解する契機にするとともに、論理的思考の力を高めることを目標にする。 |
| 事前・事後学修の内容 | 演習での議論が発展するかどうかは、何よりもまず受講生がその回の演習で課されている課題について、しっかりと予習してきたかどうかにかかっている。予習のやり方や注意点については、ここでは書ききれないが、細かい指導を行うように心がけている。 この演習では、報告などの結果の良し悪しよりも、その報告を準備するまでの過程を重視する。結果にとらわれないで、準備段階で汗をかく労をいとわないこと。 |
| 事前学修の時間:180分/回 事後学修の時間:60分/回 |