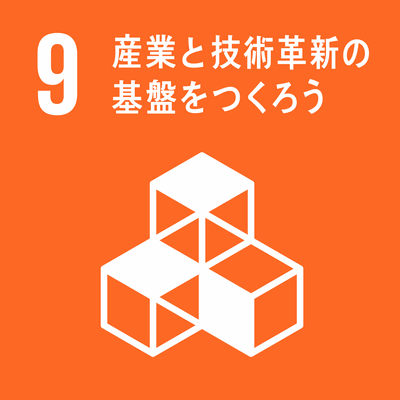シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 生物資源学部 | |
| 受講対象学生 |
資源循環学科・グローカル資源利用学教育コース 学部(学士課程) : 2年次 グローカル資源利用学教育コースの学生対象科目です |
|
| 選択・必修 | 必修 グローカル資源利用学教育コースの学生対象科目です |
|
| 授業科目名 | 農業化学実験 | |
| のうぎょうかがくじっけん | ||
| Agrochemical experiment | ||
| 単位数 | 1 単位 | |
| ナンバリングコード | BIOR-Reso-2133-002
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
前期集中 時期については別途指示する |
|
| 開講時間 |
|
|
| 授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | 生物資源校舎442室 | |
| 担当教員 | 吉原 佑 | |
| Yu Yoshihara | ||
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | この講義では各自で研究の仮説を立て、その仮説の立証のために化学・生物学実験を用いて必要なデータを求める。 実験は動物、植物、土壌を広く実験試料とし、栄養成分分析等様々な実験手法を体験する。実験結果をまとめ、仮説検証のために統計解析を行い、最後にスライドで結果を発表する。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 実験計画を考え、仮説を立て、統計を用いてそれを立証するという研究の一連の流れを訓練することができる。 基礎的な実験技術を取得することができる。 |
| 学修の到達目標 | 知識 試薬や実験器具に関する知識と取り扱い方法を学習することができる 態度 実験の知識と手順について各自で説明できるようになる 技能 学生が各研究室に配属されたのち、卒業論文の作成に必要な実験を各自で進められるようになる。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 実験結果発表40%、出席40%、実験レポート20%を予定している (60%で合格) 知識 最後の発表でこれまでに理解した知識を問う(40%) 技能 実験で培った知識を実習で活用し、そのレポートを評価する(20%) 態度 実験中の学生の姿勢や技術によって出席点を変動させる(40%) |
| 授業の方法 | 実験 |
| 授業の特徴 |
問題自己設定型PBL 実地体験型PBL プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 グループ学習の要素を加えた授業 |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | |
| 受講要件 | |
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
|---|
| キーワード | NDF、DNA抽出、食品分析 |
|---|---|
| Key Word(s) | NDF、DNA extraction, food analysis |
| 学修内容 | 1回 オリテンテーション 2回 実験方法の基礎(実験用試薬、器具の説明と取り扱い) 3回 NDF実験試料用作物の収穫 4回 NDF実験 前半 5回 NDF実験 後半 6回 食品テクスチャー分析 7回 DNA抽出① 8回 動物試料(血液)の血球と成分分析 9回 ELISA法を用いた動物ホルモンの定量 10回 DNA抽出② 11回 土壌成分分析 12回 糞中寄生虫数のカウント 13回 近赤外分光法を用いた成分分析 14回 データの統計分析についての解説 15回 分析結果のスライド発表 |
| 事前・事後学修の内容 | 事前に配布するテキストに目を通しておくこと。 実験後に、ノートを見て実験内容を振り返り、復習しておくこと。 |
| 事前学修の時間:60分/回 事後学修の時間:60分/回 |