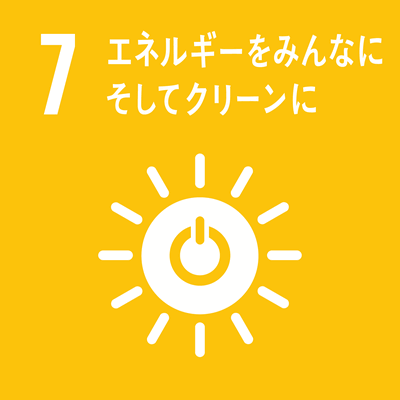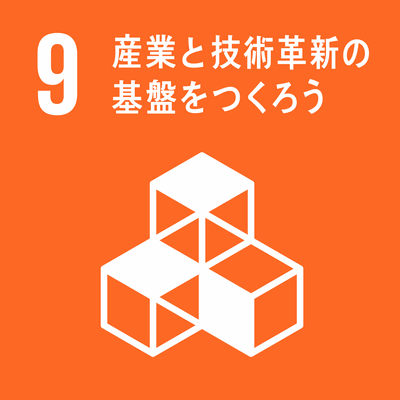シラバス表示
シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
科目の基本情報
| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 生物資源学部 | |
| 受講対象学生 |
全学科・全教育コース 学部(学士課程) : 3年次 |
|
| 選択・必修 | 必修 教育コース必修科目 |
|
| 授業科目名 | 生命機能化学演習I[微生物遺伝学教育研究分野] | |
| せいめいきのうかがくえんしゅう1[びせいぶついでんがくきょういくけんきゅうぶんや] | ||
| Seminar of Life Science Chemistry1[Microbial Genetics ] | ||
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | BIOR-Life-4132-001
|
|
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 開講学期 |
後期 |
|
| 開講時間 |
配属された各研究室の指導教員の指示に従うこと。 |
|
| 授業形態 |
ハイブリッド授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
| 開講場所 | 各研究室指定の場所 | |
| 担当教員 | 〇木村 哲哉 (生命機能化学 微生物遺伝学教育研究分野),國武 絵美 (生命機能化学 微生物遺伝学教育研究分野) | |
| 〇Kimura, Tetsuya, Kunitake, Emi | ||
| 実務経験のある教員 | 木村哲哉、公設試験研究機関において、醸造分野の中小企業の技術指導と研究開発に従事した。 國武絵美、農水省の研究機関において、微生物の利用に関する研究に従事した。 |
|
| SDGsの目標 |
|
|
| 連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
|
学修の目的と方法
| 授業の概要 | 卒業研究の準備段階として、研究に必要な知識と技術を実際に経験し学ぶ。 |
|---|---|
| 学修の目的 | 卒業研究に取り組むための基礎実験として、研究室で必要となる実験技術や知識を習得する。研究室内で他の実験者と協調して行動できるようになる。 |
| 学修の到達目標 | 研究室で必要となる微生物を扱う無菌操作、遺伝子操作の基本、微生物の単離や培養、化学分析方法などができるうようになる。研究を実施するにあたり、他の実験をする研究者にも配慮をしながら実験ができるようになる。 |
| ディプロマ・ポリシー |
|
| 成績評価方法と基準 | 授業内容の理解度70%と取り組み30% 合計が60%以上で合格 |
| 授業の方法 | 演習 実験 |
| 授業の特徴 |
プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 グループ学習の要素を加えた授業 教員と学生のやり取りは日本語でも、英語による論文や教材の講読を含んだ授業 |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | |
| 教科書 | 配布するプリント |
| 参考書 | |
| オフィスアワー | 原則として昼休み、18:00以降随時 |
| 受講要件 | 微生物遺伝学研究室で卒業研究を実施予定の人。 |
| 予め履修が望ましい科目 | 生命機能化学教育コースの実験・実習。 |
| 発展科目 | 卒業研究 |
| その他 |
授業計画
| MoodleのコースURL |
https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=5331 |
|---|
| キーワード | 微生物遺伝学、分子遺伝学、遺伝子 |
|---|---|
| Key Word(s) | microbial genetics, molecular biology, gene |
| 学修内容 | 第1回 微生物実験における無菌操作の基本(器具の滅菌、培地の作成と滅菌、大腸菌の培養) 第2回 大腸菌の形質転換(プラスミドの大腸菌への形質転換) 第3回 形質転換された大腸菌の培養 第4回 組換え大腸菌からのプラスミドの抽出(キットを使った方法)とプラスミドの定量 第5回 PCR法による遺伝子の増幅(リボソーマルRNA遺伝子のPCRによる増幅)と電気泳動による解析 第6回 PCR法で増幅した遺伝子のプラスミドへのクローニング(プラスミドの制限酵素処理とPCR断片のアガロースゲル電気泳動からの回収) 第7回 プラスミドとDNA断片のライゲーションと大腸菌への形質転換 第8回 lacZ遺伝子とITPGとX-galによるblue-white選抜についての解説と実験結果の解釈 第9回 colony PCRによる断片挿入の確認 第10回 プラスミドの抽出と制限酵素による挿入断片の確認 第11回 塩基配列の確認と配列の公共データベースによる相同性検索方法 第12回 研究室における研究テーマ(嫌気性細菌)の解説 第13回 研究室における研究テーマ(糸状菌)の解説 第14回 ラビリンチュラの分離と生態に関する研究テーマの解説 第15回 卒業研究のテーマ説明と質疑応答 微生物遺伝学研究室において対面方式で実施するため、原則として研究室にて出席すること。 |
| 事前・事後学修の内容 | 事前に予告する内容について自分で調査し理解しておくこと。疑問点をまとめること。 事後学習として、実験ノートをまとめること。結果について考察すること。 実際の授業は、講義のみでなく、実験やプレゼンテーション、ディスカッションも行うため時間通りに終了しない。1回あたりの学習時間は120分以上となるため、この時間も事前事後学習に含める。 |
| 事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |